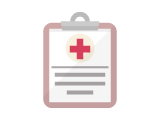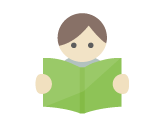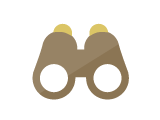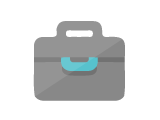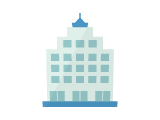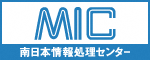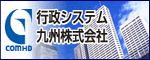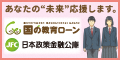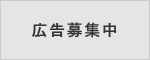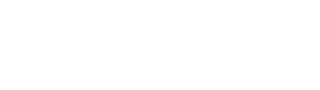更新日:2025年9月30日
ここから本文です。
鹿屋市内の県・市指定文化財一覧
県指定文化財一覧
所在地のリンクをクリックすると、展示場所や文化財マップが確認できます。
有形文化財
考古資料
| 写真 | 名称 | 所在地 | 説明 |
|---|---|---|---|
 |
短甲・衝角付胄 | 串良ふれあいセンター内 歴史民俗資料室 |
昭和25年、西祓川町中原で地下式横穴から発見された物である。 古墳時代(5世紀頃)の物と推定される貴重な資料である。 (昭和41年3月11日指定) |
 |
中尾地下式横穴墓群出土品 |
|
中尾地下式横穴墓群は、6世紀後半から7世紀初頭頃の地下式横穴墓8基から構成される。 特に6号地下式横穴墓からは象嵌装大刀、鉄剣、鉄刀、鉄鏃、耳環等、多様な副葬品が出土した。象嵌装大刀は、はばきと鐔の両面と切羽縁金具部分に銀象嵌で心葉文や二重半円文を施したものである。 これらは本県における古墳時代の副葬品の中でも、屈指の情報量と質を誇る貴重な資料である。 (平成25年4月23日指定) |
民俗文化財
有形民俗文化財
| 写真 | 名称 | 所在地 | 説明 |
|---|---|---|---|
 |
野里の田の神 |
野里町岡村 (外部サイトへリンク) |
像の高さ70cm、軟質凝灰岩でできていて、寛延4年(1751年)に作られ、鈴持ち田の神舞型の最も古いものだといわれている。 コシキを頭巾風に背中にたらしてかぶり、袖の長い上衣を着て首のところに特有の胸かざりがついており、右手にメシゲを下向きに持ち、左手は舞用の鈴をもつ、胸を突き出しひざで立っている。 (昭和43年3月29日指定) |
無形民俗文化財
| 写真 | 名称 | 所在地 | 説明 |
|---|---|---|---|
 |
山宮神社春祭に伴う芸能 | 串良町細山田堂園 |
田打、カギヒキ、正月踊が行われる。 春祭は旧正月23日であったが、現在は2月の第3日曜日に行われる。 (昭和37年10月24日指定) |
 |
王子町鉦踊り | 王子町 |
江戸時代、新田川の完成を祝い奉納されたもので、旧暦の8月28日、和田井堰にて水神様に豊作を祈念して行われる。 (令和2年4月28日指定) |
記念物
史跡
| 写真 | 名称 | 所在地 | 説明 |
|---|---|---|---|
 |
笠野原土持堀の深井戸 | 串良町細山田土持 (外部サイトへリンク) |
シラス台地の笠野原は雨が降ってもすぐ地下に吸いこまれ、長い間耕作できなかったが、江戸時代頃から少しずつ開発がされてきた。 井戸は生活用水が不足するために掘ったもので、現存する何か所かの井戸のうち最も原形をとどめている。掘られたのはだいたい文政年間から天保年間ごろと考えられている(1818~1841年)。 井戸の深さ約64m、表面の直径は約90cm、円筒形の素掘り。この井戸は、笠野原台地の開発の苦難の歴史を物語る貴重な文化財である。 (昭和57年5月7日指定) |
 |
岡崎古墳群 | 串良町岡崎 (外部サイトへリンク) |
岡崎古墳群は、肝属平野西側の台地上に立地する古墳群で、20基の古墳からなる。 4号墳は、現況で長径6m、短径5m、高さ2.2mの円墳であるが、周辺を調査した結果、元来直径20mの円墳で、周囲を幅3~5m、深さ0.5mの周溝が廻っていたことが判明した。この周溝内からは、少なくとも3基の地下式横穴墓も確認されている。 15号墳は、墳丘長25.5mの帆立貝形前方後円墳で、主体部には花崗岩製の箱式石棺があり、石棺の内外から甲冑片や勾玉、管玉等が出土した。 志布志湾沿岸の他の古墳群との関連や、本県の古墳時代の様相を知るうえで欠くことのできない遺跡である。 (平成26年4月22日指定) 平成25年4月23日指定の「岡崎古墳群(15号墳)」に追加して指定するとともに、その名称を「岡崎古墳群」に改める。 |
市指定文化財一覧
有形文化財
考古資料
| 写真 | 名称 | 所在地 | 説明 |
|---|---|---|---|
 |
古銭 |
昭和36年、田崎町老神で工事中に発見された。 前漢から元迄の中国銭で、ほとんどは北宋銭であり、室町時代に埋められたものと思われる。 (昭和37年11月15日指定) |
|
 |
板碑 | 高須町(波之上神社境内) (外部サイトへリンク) |
南北朝時代、争乱の死者の供養のため立てられた物。
(昭和43年5月27日指定) |
 |
荒平の六地蔵塔 | 天神町 (外部サイトへリンク) |
天文8年(1539年)の造立。 戦国時代の田代一族の追善供養塔であり、市内の六地蔵の中でも最も古い時代の物のひとつである。 (昭和62年5月1日指定) |
建造物
| 写真 | 名称 | 所在地 | 説明 |
|---|---|---|---|
 |
中津神社本殿 | 上高隈町 (外部サイトへリンク) |
正平6年(1351年)高隈郷の鎮守として創建。本殿は承応2年(1653年)造営。 構造は、三間社流れ造り柿葺きである。 (昭和47年3月30日指定) |
 |
大園橋 |
祓川町 (外部サイトへリンク) |
大園橋は明治37年5月に完成し、めがね橋として親しまれている。 全長30m、橋の巾3.1m、高さ約5m、橋床は複式アーチ型(めがね橋)。橋脚は川床にがっちりとし、堅牢優美。 当時の石造技術としては抜群で、大隅地方に数少ないめがね橋として貴重である。 (昭和63年10月4日指定) |
彫刻
| 写真 | 名称 | 所在地 | 説明 |
|---|---|---|---|
 |
花岡町花岡山浄福寺の小型阿弥陀如来尊像 | 花岡町(花岡山浄福寺) (外部サイトへリンク) |
浄福寺にある手の中に収まるほどの小さな阿弥陀像である。高さ3.8cm、幅2.1cmの厨子の中におり仏像の高さは0.9cm程である。 これは花岡島津家六代久誠の妻時子が所持していた物で、夫婦とも密かに礼拝していたと言われている。 (平成13年9月6日指定) |
民俗文化財(有形民俗文化財)
有形民俗文化財
| 写真 | 名称 | 所在地 | 説明 |
|---|---|---|---|
 |
含粒寺石像群 | 南町(含粒寺) (外部サイトへリンク) |
10基の石像(地蔵2板碑1仁王像4観音像2六地蔵1)はそれぞれの特徴が良く表現され、芸術品として価値がある。
(昭和56年8月19日指定) |
 |
仁王像 | 輝北町市成 (外部サイトへリンク) |
市成登見の丘の麓にある一対の仁王像。昔から風邪(百日咳)を治す仁王像として親しまれ、病が治ると火吹き竹を供えていた。 市成が島津家支流の敷根氏の所領であったころ、菩提寺の法城山両足寺の山門に据えられた像で、今から約600年前の室町時代の作と伝えられている。 「廃仏き釈」の被害を免れるために、地中に埋めていたのを、現在の管理者の祖父吉水治左衛門が現在地に安置した。 口をあけている像を「阿像」、口を結んでいる像を「吽像」という。五十音でも梵字でも「阿」は言葉の始まりで、「吽」は言葉の最後になっている。 (昭和56年12月16日指定) |
 |
歌丸の六地蔵 | 輝北町上百引 (外部サイトへリンク) |
寛保3年(1743年)に建立されたもので、裏面には「奉建立庚申供養青面金剛」とある。塔身の六面には、仏像と梵字がそれぞれ刻まれる。
(昭和56年12月16日指定) |
 |
一石五輪塔 | 輝北町上百引 (外部サイトへリンク) |
鎌倉時代前期の軽石製の逆修供養塔と考えられ、昔から「殿さあんの墓」として言い伝えられている。 五輪塔は五個の石造物を積み重ねたようにできており、下段より方形で地輪、二番目が円形で水輪、三番目が三角形で火輪、四番目が半月形で風輪、最上段が空輪となっている。 一般的に、空・風輪は一個で、火・水・地輪は各一個で構成されているが、ここの五輪塔は、材料に軽石を使い、一個の石で造られているので一石五輪塔といい、輝北地域でも数基が確認されているだけである。諏訪の一石五輪塔は完全に近い姿で安置されている。 【逆修(ぎゃくしゅ)】生きている間に、自分が死んだ後の冥福のために行う仏事。 (昭和56年12月16日指定) |
 |
庚申地蔵 | 輝北町平房 (外部サイトへリンク) |
元禄3年(1690年)に庚申講衆中が建立したものである。 「奉庚申供養」「元禄三庚歳十一月二十七日」「当所中与女性讃物立之石塚」の刻銘がある。 (昭和56年12月16日指定) |
 |
丸山寺の石塔群 | 輝北町下百引 (外部サイトへリンク) |
真言宗坊津一乗院の末寺であった丸山寺ゆかりの古石塔群である。 なかでも、高さ3.23mにも及ぶ巨大五輪塔と、月輪塔は大隅半島では大変珍しく、勢力の大きさが偲ばれる。 (昭和56年12月16日指定) |
 |
福師岳の三尊石仏 | 吾平町上名 (外部サイトへリンク) |
整備された福師岳遊歩道の中腹に位置する。一枚岩に釈迦・文殊菩薩・阿弥陀の三尊が彫られている。
(昭和58年3月5日指定) |
 |
下方の六地蔵 | 輝北町市成 (外部サイトへリンク) |
宝珠・笠石・がん部・中台・憧身・基礎からなり、全長は2mにもおよぶ大きなものである。 六角形の各面にはそれぞれ異なった仏像が浮き彫られ、仏像によって安置の方位まで定められている。 この六地蔵は「イボ」の神としてしたしまれ、大豆を供える風習がごく最近まで残っていた。指が入るぐらいの穴が数多くみられる。 (昭和58年3月5日指定) |
 |
谷田の六地蔵 | 輝北町諏訪原 (外部サイトへリンク) |
幕末から明治の初めに起こった廃仏毀釈運動を恐れて田圃に埋められたもので、その後に掘り返された。破壊を免れた貴重な文化財である。
(昭和58年3月5日指定) |
 |
下平房の田の神 | 輝北町平房 (外部サイトへリンク) |
右手にメシゲ、左手にスリコギを持つユーモラスな表情の田の神で、田植え前には豊作を祈って、集落の人々によってお化粧がなされる。
(昭和58年3月5日指定) |
 |
中福良の田の神 | 輝北町諏訪原 (外部サイトへリンク) |
シャモジとスリコギを持ち、両肩に乗せている。眼の彫りが大変深い。
(昭和58年3月5日指定) |
 |
宮園の田の神 | 輝北町市成 (外部サイトへリンク) |
左手にスリコギを持ち、肩にかついでいる。右手にも何か持っていたと思われるが、現在は欠損して分からない。
(昭和58年3月5日指定) |
 |
歌丸の田の神 | 輝北町上百引 (外部サイトへリンク) |
弘化4年(1847)建立。製作者は「佐吉」とある。左手にスリコギを持ち,肩にかついでいる。
(昭和58年3月5日指定) |
 |
中福良の八幡神社境内の田の神 |
吾平町上名 (外部サイトへリンク) |
大きなシキを背後に長く垂らして被っている。立像鍬持ちの田の神でほぼ完形で残っている。
(昭和60年8月21日指定) |
 |
飴屋敷の観音 | 吾平町上名 (外部サイトへリンク) |
凝灰岩の石像で、台座に「惟時(日編に乏)享保六辛丑六月吉祥日」の銘刻があり、均整の取れた美しい像である。※享保六年(1721年) 吾平地区内に9基の観音像があるが、そのうち8基は上名地区に集中している。 (昭和61年1月27日指定) |
 |
長谷観音 長谷城跡中世石塔群 |
祓川町(大園観音堂) (外部サイトへリンク) |
長谷観音は、奈良県長谷寺の影響を受けた長谷信仰の南限に近い観音で、わが国の仏教の源流を探る上で貴重な物である。 石塔群は、冨山三郎義遠が安元年間頃(1175年~)この地に来て長谷氏を名乗り田地開発を行った当時の長谷一族の逆修供養塔群で、長谷氏の相輪文様もはっきりとし歴史的に貴重な資料である。 (昭和62年5月1日指定) |
 |
春日神社境内の観音像大乗妙典読誦碑 |
打馬1丁目 (春日神社境内) |
これらは江戸時代中期の造立と推定され、当時の信仰形態を知る資料として貴重な物である。
(昭和62年5月1日指定) |
 |
烏ヶ山月待供養塔観音 |
南町烏ヶ山 (外部サイトへリンク) |
この観音像は、享保18年(1733年)造立で歴史的・芸術的価値が高い。 月待供養塔は県下にも数少なく、江戸時代の庶民の信仰を知る上で貴重な資料である。 (昭和62年5月1日指定) |
 |
木場薬師および薬師堂の鰐口 | 祓川町 (外部サイトへリンク) |
仏像自体の作りも古く美麗、文政8年の鹿屋名勝誌にも記録がある。 鰐口は、永正4年(1507年)の作で、多くの刻字があり貴重な物である。 (昭和62年5月1日指定) |
 |
上野寺田の 庚申塔 |
上野町 (外部サイトへリンク) |
中国の道教の三尸説からきた庚申信仰の具象物で、特に江戸時代には庶民の間で崇拝されていた。享保19年(1734年)造立。刻字からその趣旨がわかる貴重な物である。 (昭和62年5月1日指定) |
 |
車田の田の神 | 吾平町上名 (外部サイトへリンク) |
田の神像に山水を表現したと思われるものが刻み添えられている。 像高93.5cm、山水の高さは52cm。渦巻き模様のシキを被り、袖の長い上衣と袴をつけている。左手はメシゲ、右手はスリコギをもつ。山水の面には磨崖仏風に小仏らしいものが浮き彫りしてある。また頭上にも胸元にもさらに小さい仏像がつけてある。 この山水は修験道場としての山を示していて、その山から現れた効験あらたかな像を田の神としたことを教えているものと思われる。 (昭和62年8月22日指定) |
 |
大牟礼の田の神 | 吾平町上名 (外部サイトへリンク) |
右足が左足より少々上げた台石に乗せてあり、歩く姿を表現した山伏僧の風貌をしのばせる像である。
(昭和62年8月22日指定) |
 |
大塚原の六地蔵塔 | 串良町有里上大塚原 (外部サイトへリンク) |
所在地大塚原集落、坂元氏宅の外側の十字路の角に立っている。基壇、基石は埋没しており、奉寄進串良有里村下(以下埋没不明)と刻まれている。
(昭和63年3月14日指定) |
 |
生栗須の六地蔵塔 | 串良町細山田生栗須 (外部サイトへリンク) |
塔身の南西側に「干時延寶五丁乙二月彼岸」、北東側に「謹奉造立六道能化像以」「爲月清花詠信士形像」、西側に刻字の跡がある。 不明記銘のある六地蔵は多いが、年代から考えると串良町内に現存する像形のしっかりしたものでは一番古いものである。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
柚木原墓地の平面六地蔵塔 | 串良町有里山下 (外部サイトへリンク) |
六面体の六地蔵塔はあるが、平面に六地蔵が刻出してある本地区ではきわめて貴重なものである。
(昭和63年3月14日指定) |
 |
中郷の田の神像 | 串良町有里中郷 (外部サイトへリンク) |
中郷集落中央部の、公民館内にある。 高さ25cmの正方形の台座の上に南向きに立っている。袖長の長衣を纏い、シキを被り、右手にスリコギ、左手にメシゲを持ち、右膝を少し立てている。像の背面に「天保五甲午三月初丑奉建立串良有里村中方限」と刻んである。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
岡崎上の田の神像 | 串良町岡崎上 (外部サイトへリンク) |
岡崎上公民館前にあり、台は軽量ブロックで本来のものではない。 像の高さ100cm、頭にシキを被り、右手にスリコギ、左手にメシゲを持っている。長袖の衣をまとい、短袴をつけている沓履きの立像である。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
甫木池の田の神像 | 串良町有里中甫木 (外部サイトへリンク) |
中甫木集落の甫木池南側道路をはさんだ市有地右側にある。左側の水神桐と共に、南向きである。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
田中屋敷の田の神像 | 串良町細山田下中 (外部サイトへリンク) |
傾いた頭にシキを浅く被り、右手にメシゲを持っている。容姿が滑稽、且つ妖艶な風情があり、女性を連想させる。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
中山池の庚申塔 | 串良町上小原中山上 (外部サイトへリンク) |
中山池の公園横に、水神祠とともに並んで建っている。 塔身の縦100cm、幅25cm、横57cmの台の上に建ち、船の形の碑に浮き彫りされた像が正面にあり、右側に「享和二年奉建立壬戌十一月吉日」左側に「中山中人数八拾人」に記銘がある。江戸時代のこの地域の人々の庚申信仰をしのばせている。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
鳥之巣の庚申塔 | 串良町有里鳥之巣 (外部サイトへリンク) |
有里鳥之巣吉留氏宅の石垣の門の西側山林内にあり、南向きに立ち大きいものである。彫像部左側面に寛延四辛未五月廿三日とある。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
下名真角の田の神など | 吾平町下名 (外部サイトへリンク) |
吾平町内で確認されている田の神で最古のもの。旅僧の歩行型の立像である。 (平成2年3月28日指定) |
 |
上名苫野の田の神など | 吾平町上名 (外部サイトへリンク) |
2像ある。1つは、左手にメシゲを持ち手を上げ、右手にスリコギを持っている。もう1つは、左手にメシゲ、右手にスリコギを持ち両手を交差している珍しい像である。 (平成2年9月21日指定) |
 |
上名角野の山本観音 | 吾平町上名 (外部サイトへリンク) |
飴屋敷の観音と同時期の像立である。後背が紛失しているが、ほぼ完形を留めており立派な観音である。 (平成2年9月21日指定) |
 |
上名新地の観音 | 吾平町上名 (外部サイトへリンク) |
完形のまま残っている立派な像である。南隣に石灯籠がある。新地とっば(湯治場・冷泉)の上にあり、住民に親しまれてきた像である。 (平成2年9月21日指定) |
 |
六地蔵塔 | 下高隈町柚木原(墓地内) (外部サイトへリンク) |
鹿屋市内にある六地蔵のうちで最も古い天文4年(1535年)に造られており、荒平の物より4年、含粒寺の物より30年も古く、歴史的に貴重な物である。 (平成7年1月11日指定) |
 |
小烏神社の庚申塔 | 野里町(小烏神社) (外部サイトへリンク) |
この庚申塔は江戸時代前期の延宝2年(1674年)に造立されたもので、青面金剛を本尊とする庚申塔では県内で最も古いと言われる。 江戸時代中期以降の庚申塔より端正で簡素であり、庚申信仰の歴史を探る貴重な資料である。 (平成7年1月11日指定) |
 |
含粒寺跡 | 吾平町上名 (外部サイトへリンク) |
明治2年の廃仏き釈により廃寺となったが、島津元久の唯一の息子である仲翁和尚(ちゅうおうおしょう)によって開かれた。 寺一帯の山はもと鶴ヶ岡と称し、その形が中国の仏教の聖地「廬山」に似ていたので、和尚は山中に多くの竹を植え「小廬山」と称した。 寺の中に石の塔があり、その中には僧侶等のお墓も残っている。 含粒寺は山中八景といって、当時は八つの美しい景色を見ることのできる場所であった。今でも外観はその当時をしのぶことができる。含粒寺は約440年間続いた。 (平成13年12月5日指定) |
 |
下名真角の古石塔 | 吾平町下名 (外部サイトへリンク) |
馬頭観音1基・石灯ろう1基。左手に弓を、右手に矢1本を持ち、背中に矢を2本背負い、勇壮活発な面構えの像である。 (平成15年12月12日指定) |
 |
徳留の虚空蔵菩薩像 | 輝北町市成 (外部サイトへリンク) |
頭は五知の宝冠をいただき、右手に宝剣、左手に宝珠を持ち、蓮華座に坐す。「奉寄進」「宝暦十年戊辰」「十一月十三日」「徳留村の徳蔵」などの刻銘がある。 (平成17年11月8日指定) |
民俗文化財(無形民俗文化財)鹿屋市の無形民俗文化財の紹介
無形民俗文化財
| 写真 | 名称 | 所在地 | 説明 |
|---|---|---|---|
 |
祓川町八月踊 | 祓川町 |
祓川町で江戸中期から行われてきた踊りで水神祭で奉納される。旧暦の8月28日に行われる。 (昭和37年11月15日指定) |
 |
大姶良西方棒踊 | 大姶良町(岩戸神社) |
旧大姶良郷社であった岩戸神社に伝わる神事で、旧暦8月午の日に五穀豊穣、厄病退散、家内安全を祈念して奉納される。 (昭和39年2月15日指定) |
 |
鈎引き祭 | 上高隈町(中津神社) |
中津神社に伝わる300有余年の歴史を持つ神事で、2月の第3日曜日に行われる。農林業の発展を祈念し、雄鈎・雌鈎を引き合い勝負をする。 (昭和40年8月20日指定) |
 |
しか祭 | 田崎町(七狩長田貫神社) |
七狩長田貫神社(田崎神社)に伝わる神事の一つで神狩祭とも言う。狩猟時代からの歴史を物語る祭りである。 (昭和41年4月1日指定) |
 |
八月口説踊 | 川東町(新田川沿い) |
旧暦の8月28日、和田いぜき、川東町鶴田池、光同寺池の各水神に五穀豊穣を祈って奉納されたものである。 (昭和46年4月12日指定) |
 |
田の神舞 | 南町(年貫神社) |
年貫神社に伝わる神事で、五穀豊穣を祈り奉納される。田の神と農民の珍問答が特徴である。 (昭和46年4月12日指定) |
 |
朝倉太鼓踊り | 輝北町諏訪原 |
江戸末期、加世田の職人から伝えられたものといわれ、「川踊り」とも呼ばれた。鉦打ちは太鼓打ちに、太鼓打ちは鉦の音に合わせて、足取り軽く隊形を整えながら踊る。 (昭和61年12月5日指定) |
 |
高須町の刀舞 | 高須町(波之上神社) |
旧暦6月15日八坂神社の祇園祭に行われる神楽舞で、刀・長刀・鬼神・田の神・弓の5つの舞の総称である。境内で祭典を行い、5つの舞を同時に舞いつつ御輿と共に町内をねりまわる。 (平成13年9月6日指定) |
 |
川原園井堰の柴かけ | 鹿屋市串良町細山田字桜田 (一級河川串良川下中橋下流) |
約350年前(江戸時代)から現在まで続くこの柴かけは、山からマテバシイを切り出し、竹で束ね柴束を作り、串良川に運び、水神祭等の後に、地域の人々の手で柴束を掛ける。掛け終わるころには、水位が上昇し、取水口から有里用水に水が供給される。 また、平成12年から平成15年に文化庁が実施した農林水産業に関する文化的景観調査研究報告で「重要地域」に選定され、景観としても、全国的に貴重なものである。 さらに、日本で唯一残されている「柴堰」であり、本市の農業史を後世に伝える文化財として極めて貴重である。 (平成29年4月14日指定) |
記念物(史跡)
| 写真 | 名称 | 所在地 | 説明 |
|---|---|---|---|
 |
鶴亀城本丸跡 | 串良町岡崎鶴亀 (外部サイトへリンク) |
応永末期から戦国期にかけて築城改築された城で、串良町岡崎の台地東部に舌状に突出した多郭式台地端城であった。現存する唯一の郭で、貴重な文化遺産である。 (昭和48年12月1日指定) |
 |
地頭館仮屋跡 | 串良町岡崎鶴亀 (外部サイトへリンク) |
旧串良小学校敷地一帯。 串良城(鶴亀城)本郭・二郭・三郭の山麓を貫流する有里用水路(寛文十一年開設)と、本郭の東南東から三郭の山麓近くに大きく湾曲蛇行していた串良川旧河川(大正初期改修)の中間の平坦な山麓一帯の概ね2500平方メートル位の敷地を、南面35メートル・東面55m、高さ約2m程度の平積石垣で囲み、東面中央寄りに仮屋正門・同北端に通用門を設けて築造されていた。 (昭和48年12月1日指定) |
 |
正安の五輪塔 | 吾平町麓3599 (外部サイトへリンク) |
姶良名勝志(文政7年(1824年))には、上名村に薗入寺という寺が昔あったと記されている。この五輪塔は、薗入寺の阿弥陀堂の脇にあったもので、「正安元季歳次己亥十月六日孝子等敬白」と記されている。 記年名の石塔では、大隅半島におけるもっとも古い部類に属するものであり、全長1.9mというおごそかで立派なものである。※正安元年(1299年) (昭和53年5月10日指定) |
 |
上名赤野の石塔群 | 吾平町上名 (外部サイトへリンク) |
五輪塔1基、宝塔1基、板碑2基、奉寄進の文字が刻まれた石塔1基、五輪塔残欠 この石塔群は同一族のものであるという。宝塔の相輪上部が欠損していてまことに惜しいのであるが、板碑2基が揃っているのはまれである。しかも中心人物をとりまく他の逆修塔の一部も残欠ではあるが保存されている。 (昭和53年5月10日指定) |
 |
下名川北天神原の五輪塔 | 吾平町上名 (外部サイトへリンク) |
五輪塔2基・水輪2基・空輪1基で下名川北町内会にあったものを移設したものである。鎌倉時代後期頃である。
(昭和55年8月23日指定) |
 |
花岡島津氏歴代墓地 | 花岡町 (外部サイトへリンク) |
花岡島津家歴代のお墓がきちんと並び、堂々としてりっぱな風格と、男性と女性の区別、お墓の形を区別するなどの特徴をもっており、学術研究上から貴重なものである。 花岡島津家は、始祖久儔(ヒサトモ)以来10代直久(ナオヒサ)まで続き、島津八家の中、一門家につぐ大身分としてりっぱな家柄を持った家筋であった。また、二代久尚(ヒサナオ)婦人岩子姫は、高隈山ろくから清流を引く用水路の整備をするなど、花岡の農業を改善した人物である。 (昭和56年8月19日指定) |
 |
観音渕中世供養塔群 | 下高隈町 (外部サイトへリンク) |
鎌倉時代の初めから戦国時代にかけての供養塔群で、約90基の石塔がある。これは開田作業や戦乱のときの逆修供養塔と見られる。 (昭和56年8月19日指定) |
 |
白寒水城跡五輪塔群 | 串良町下小原白寒水 (外部サイトへリンク) |
鎌倉時代初期とみられる納骨五輪塔(骨が入った五輪塔)1基を含んで、鎌倉期25基、南北朝期の肝付氏系統11基を含んで室町前期の五輪塔47基、及び南北朝中期ごろの全高136cmの梵字刻出の板碑1基など、70数基に及ぶ串良地域内最大の五輪塔群。 石塔は通称フィジョ山と呼ばれる白寒水城跡二郭内に、11面観音と共に整然と保存されている。 (昭和57年1月22日指定) |
 |
中郷小野原墓地の納骨宝塔 | 串良町有里中郷 (外部サイトへリンク) |
推定鎌倉末期ごろの肝付家主流とみられる納骨宝塔は、正面と右側に薬師如来像、左側には烏帽子水干姿の合掌人物像が浮彫りされており、古石塔としてまったく類例をみない宝塔である。 浮彫りされている薬師如来像は、有名な鎌倉三尊薬師の一つにある薬師像と同じく外傷の担当を意味する三角巾を膝においた、特殊な姿勢の薬師如来が浮彫りされており、烏帽子水干姿の高貴な人物が薬師如来に合掌祈念する姿は、極めて暗示的である。 肝付兼藤の納骨宝塔とする説が有力視されている。なお、納骨孔にはわずかながらも骨灰が内蔵されている。 (昭和57年1月22日指定) |
 |
上名西目川路の逆修塔群 | 吾平町上名 (外部サイトへリンク) |
西目川路の山林内に埋まっていたものを復元したもの。五輪塔・宝塔・板碑合わせて37基ある。 (昭和57年5月1日指定) |
 |
北原氏逆修古石塔群 | 串良町細山田平瀬 (外部サイトへリンク) |
推定平安末期から鎌倉初期ごろまでの間、この地方の開拓に当った豪族の、下僕たちの粗末な人物像12面を刻出した7基の供養碑をはじめ、五輪塔数基、宝搭5基が保存されている。 (昭和57年5月11日指定) |
 |
加瀬田ヶ城跡 | 輝北町平房 (外部サイトへリンク) |
高山本城と三股城の中間に位置することから、島津・肝付の壮絶な戦いが繰り返され、南北朝双方が交互に支配した。 北側はシラスの絶壁、東南側は急斜面で、両側は堀が造られ、城内には井戸もあったとされる。攻め難く守り易い城であった。 (昭和58年3月5日指定) |
 |
朝倉の隠れ念仏洞 | 輝北町諏訪原 (外部サイトへリンク) |
江戸期、薩摩藩の一向宗禁制による弾圧を免れるために造られた念仏洞で、暗夜や嵐の日などに、こっそりここに集まり、ご本尊を拝み、読経した跡である。 洞穴は、人里離れた山奥にあり、人声や念仏、読経が外に漏れないように、クランク状に彫られている。ノミ痕もはっきりと残っている。 (昭和58年3月5日指定) |
 |
下名真角の金剛経一万巻読誦所碑 | 吾平町下名 (外部サイトへリンク) |
戦国時代に金剛経を一万巻読誦した記念に建てられた石碑である。大隅半島でも非常に珍しいものである。 (昭和59年4月20日指定) |
 |
下名井神島の宝篋印塔 | 吾平町下名 (外部サイトへリンク) |
宝篋印塔2基・他相輪のみ2基。宝篋印塔のうち1基は肝付氏主流、もう1基は検見崎氏のものである。室町~戦国時代中期頃のものである。 (昭和60年1月22日指定) |
 |
蓮台寺跡の中世石塔群 | 高須町 (外部サイトへリンク) |
南北朝・戦国時代の石塔、江戸時代の六地蔵塔など総数約30基あまりを数える。時代的にも層が厚い大石塔群で、中世史解明に貴重なものである。 (昭和62年5月1日指定) |
 |
伊地知氏宅の五輪塔 | 高須町(旧駅前) (外部サイトへリンク) |
南北朝時代、南朝方勤王僧として正平3年(1348年)高須に来て波之上神社に立願文を捧げた昌光僧都の逆修供養塔と推定される、鹿屋市一巨大な五輪塔で貴重なものである。 (昭和62年5月1日指定) |
 |
上谷の板碑 | 上谷町 (外部サイトへリンク) |
中世後期の永禄9年(1566年)に夫妻の逆修供養塔として建立されている。通常と異なり頂部が楕円形になるという、大隅でたまに見られる特徴をもつ板碑である。 (昭和62年5月1日指定) |
 |
獅子目清水の石塔群 | 獅子目町清水 (外部サイトへリンク) |
鎌倉末期から江戸時代に及ぶ石塔群で戦乱期の逆修供養塔群、伊集院三河守の追善供養塔、正応寺の僧侶の供養塔など多くの石塔を数える。 (昭和62年5月1日指定) |
 |
立小野の古石塔群 | 串良町細山田立小野 (外部サイトへリンク) |
鎌倉末期から室町前期にわたる肝付氏系統の宝塔21基、五輪塔20基が復元されている。宅地造成の際に、夥しい石塔が埋込まれた由で、町内でも珍しく多数の古石塔が実在したことが分かる。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
アンダ堂墓地古石塔群 | 串良町細山田馬掛 (外部サイトへリンク) |
鎌倉後期から室町後期の五輪塔25基、宝塔6基が復元されている。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
松崎観音堂の古石塔群 | 串良町上小原松崎 (外部サイトへリンク) |
松崎の観音堂境内にあり、戦国期の肝付氏・富山氏系の五輪塔15基と、応永期の肝付氏系の宝塔10基がある。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
北郷どん墓地古石塔群 | 串良町下小原南 (外部サイトへリンク) |
通称ホンゴウドンの墓と呼ばれているが、島津義久の代に、北郷時久の四男北郷掃部介久村が小原村三千石を与えられ、その久村の宝篋印塔を中心に肝付氏宝篋印塔2基宝塔5基五輪塔14基が整然と復元されている。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
野崎屋敷の古石塔群 | 串良町下小原南 (外部サイトへリンク) |
南北朝初期と推定される納骨宝塔2基納骨五輪塔2基が野崎氏庭園の一隅に保存されている。 全高1m余の宝塔の台座はレンゲ紋様が刻出されており、相輪の一部が損傷しているが法輪8基が数えられ、相輪請花伏鉢の紋様も、この地方では見られぬ特殊な紋様で、中郷古石塔と関連して、源盛貞に関係あるのではとの疑問も含め、今後の学術研究上極めて貴重な古石塔である。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
下名川北の石塔群 | 吾平町下名 (外部サイトへリンク) |
宝塔5基・五輪塔24基・その他数10基の残欠石塔からなっている。中世において繁栄した得丸氏一族のものと思われる。
(平成2年2月1日指定) |
 |
門前中用水路の水神碑及び井堰改修記念碑 | 吾平町上名 (外部サイトへリンク) |
明暦元年(1655)に完成した中用水路の、安永9年(1780年)に改修した際に祭られた水神と明治20年の改修工事の記念碑である。 (平成2年3月28日指定) |
 |
鵜戸神社境内の野町観音 | 吾平町麓 (外部サイトへリンク) |
市街地の十字路交差点にあったものを鵜戸神社境内に移設したもの。優美で柔和な容姿の菩薩である。 (平成2年3月28日指定) |
 |
玉泉寺跡の住職の供養墓など | 吾平町上名 (外部サイトへリンク) |
応永2年(1395年)に越後国源翁和尚開山。20世続く由緒ある寺であったが、明治の廃仏毀釈により廃寺となった。現在は公園として整備されている。 (平成2年9月21日指定) |
 |
下名鳥淵観音 | 吾平町下名 (外部サイトへリンク) |
錦江町へ向かう県道沿いにある。天然の岩屋の中に座している観音で、鳥淵とは地名のことである。 (平成2年9月21日指定) |
 |
上小原4号古墳 | 串良町上小原下方限 (外部サイトへリンク) |
旧串良町と肝付町のほぼ境界に位置する古墳群の中央に位置し、内陸部にある前方後円墳では、南限であり極めて考古学的価値が高い。 (平成12年10月6日指定) |
 |
岡崎20号古墳 | 串良町岡崎 (外部サイトへリンク) |
岡崎古墳群の中心地域にあり、本地域で最も規模の大きい大型の前方後円墳であり、極めて考古学的価値の高い前方後円墳である。 (平成17年6月24日指定) |
 |
海軍航空隊笠野原基地跡の川東掩体壕 | 川東町8206-1 |
掩体壕とは、戦闘機等を敵の爆撃から守るために建設されたもので、コンクリート製でかまぼこ型のものが多い。笠野原基地では200基余り建設されたが、この掩体壕が当時の姿を残す唯一のものである。 戦争の記憶や笠野原に航空基地があったことを後世に伝える貴重な文化財である。 (平成27年6月26日指定) |
 |
海軍航空隊串良基地跡の地下壕 電信司令室 |
串良町有里4963-7 |
この地下壕は特攻隊員との連絡を行い、最後の通信を受け取っていた場所である。 深さ約7m、全長約51m、一番広い通信室は奥行き15m、幅4mあり、これを主室として通路、小部屋等で構成されている。保存状態も良好であり、戦争の記憶を後世に語り継ぐ貴重なものである。 (平成27年6月26日指定) |
記念物(天然記念物)
| 写真 | 名称 | 所在地 | 説明 |
|---|---|---|---|
 |
いぬまき | 新生町(熊野神社) (外部サイトへリンク) |
中央公園近くの熊野神社境内にあり、高さ約15m、幹まわり約6.3mの県下でも珍しいいぬまきの大木である。 (昭和43年5月27日指定) |
 |
クス | 田崎町(七狩長田貫神社) (外部サイトへリンク) |
クスノキ科の常緑高木。樹齢約800年で植物学上貴重である。根回り10.8m高さ24m。 日本にはクスノキの巨木が多く、国の天然記念物に指定されたものが30本もあり、そのうち3本は県内の湧水町(旧蒲生町)、肝付町、志布志市にある。防虫剤としても使われた樟脳がとれ、材質もいいので昔から利用されている。 (昭和48年1月16日指定) |
 |
大賀ハス | 串良町岡崎鶴亀 (外部サイトへリンク) |
千葉県検見川地区で発掘された2000年以上昔(弥生時代)のハスの実から発芽・開花させたもの。 故国分重春先生(元串良中学校教諭)の指導のもと、株分けによって現在まで生育されている。 (平成23年2月23日指定) |
 |
苫野川産カワゴロモ | 吾平町苫野川 (外部サイトへリンク) |
カワゴロモは熱帯植物で、南九州にのみ分布する。苫野川産のカワゴロモは生育上最適な環境で自生しており、肝属川水系で唯一の生育地となっている。 (昭和55年8月23日指定) |
 |
諏訪両神社の古木 | 輝北町上百引 (外部サイトへリンク) |
国道504号沿いの諏訪集落活性化センターの東側約100mの下側の諏訪両神社境内にある。鳥居をくぐってすぐ目に付くイチョウは目通り9m、高さ19.8m。 モミの木とイヌマキの木は寄り添うように立っており、モミは目通り4.75m、高さ32.8m、イヌマキは目通り3.75m高さ22mあり、いずれも樹齢は約400年以上といわれている。 (昭和56年12月16日指定) 令和元年6月13日一部指定解除(モミ) |
 |
北原墓地の銀杏 | 串良町細山田平瀬 (外部サイトへリンク) |
樹齢700年と想定され、周囲が3.6m高さ18mを越す巨木であり、本地区では非常に珍しい。 (昭和57年5月11日指定) |
 |
山宮神社境内のナギ | 串良町細山田堂園 (外部サイトへリンク) |
樹齢300年と想定され、周囲が2.5m高さ20mを越す巨木であり、本地区では非常に珍しい。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
事代主神社境内のクス | 串良町岡崎諏訪下 (外部サイトへリンク) |
樹齢450年と想定され、周囲が5.8m高さ21mを越す巨木であり、本地区では非常に珍しい。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
十五社神社境内の銀杏 | 串良町有里中郷 (外部サイトへリンク) |
樹齢260年と想定され、周囲が5.9m高さ20.5mを越す巨木であり、本地区では非常に珍しい。 (昭和63年3月14日指定) |
 |
横尾岳のひぜんまゆみ | 大姶良町(横尾岳公園内) (外部サイトへリンク) |
ひぜんまゆみはニシキギ科の植物で、県内では薩摩半島野間池近くに若干本、大隅半島には1、2の町に2、3本あるだけ。 横尾岳公園は貴重な自生地で十数本が生えており、ここにまとめて保護林としている。 (昭和63年10月4日指定) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.
 文字サイズ
文字サイズ