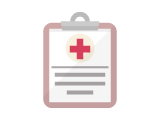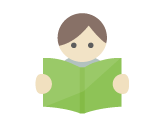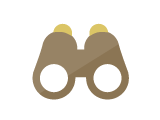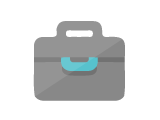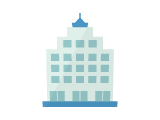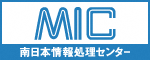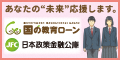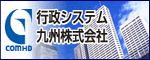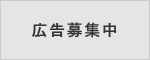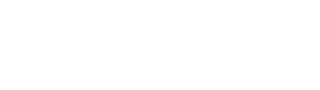更新日:2025年2月28日
ここから本文です。
施政方針(令和7年3月鹿屋市議会定例会令和7年2月19日)
-はじめに-
令和7年3月鹿屋市議会定例会の開会に当たり、市政運営に関する所信の一端を申し上げますとともに、今回、提案しております予算案等について御説明し、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御支援を賜りたいと存じます。
先月、本市の基幹作物であるさつまいもの生産者や消費者、事業者など関係者が一体となってさつまいもを楽しむ「おいもフェスかのや」を2週間にわたって開催しました。
期間中は、JA直売所などでの特設コーナーのほか「カノ屋台」とのコラボイベントや飲食店での料理の提供など「おいものまち・かのや」を実感できるイベントを実施しました。
26日にはメインイベント「大甘藷祭」を開催し、30店舗を超える「さつまいも」に特化した販売ブースをはじめ、かのやばら大使に新たに就任されたフランス料理人・上柿元シェフによる特製スープの提供や、高校生スイーツコンテストなどを実施し、多くの人で賑わいました。
来場者からは「様々な芋の商品を同時に見ることができて楽しかった」「芋好きには紹介したいイベントだと思った」などの声が寄せられ、さつまいもの奥深さを体感していただきました。
スポーツを通じてより多くの方々が、健康で充実した生活を送れるよう、鹿屋体育大学と「スポーツ実施率日本一共同宣言」を行いました。
これまで、こどもから高齢者までを対象とした体力づくりや健康増進の取組をはじめ、スポーツ合宿の推進、大学スポーツを通じた地域活性化など、様々な分野で連携した取組を進めております。
スポーツ実施率向上に向けて、ウォーキングや「ながら運動」の普及など、更に連携を深めて、心身ともに健康で幸せなまちづくりに取り組んでまいります。
今月22日には、CIELBLEUKANOYAが参戦するJプロツアーの開幕戦「鹿屋・肝付ロードレース」、また、今月から来月にかけては、野球の大規模交流戦「薩摩おいどんリーグ」や「レディースプロボウリングトーナメント」の2025シーズン開幕戦が開催されます。
市民の皆様をはじめ、たくさんの方々に会場にお越しいただき、スポーツの持つ魅力を味わっていただきたいと思います。
マリンポートかごしまと鹿屋港を結ぶ新たな定期航路が、8日から就航しております。
本市としましては「新たな玄関口」となる定期航路が、多くの方々に利用され、地域経済の発展につながるよう、観光利用の促進や二次交通の確保について関係者と協議、検討を行ってまいります。
先月開催された第8回和牛甲子園において、鹿屋農業高等学校が枝肉評価部門で、2年連続となる最優秀賞を受賞しました。
出場した生徒をはじめ関係者の皆様の日頃の御尽力に敬意を表しますとともに、今後の更なる御活躍を祈念申し上げます。
令和6年度鹿児島県広報コンクールにおいて、広報かのや11月号が、広報紙部門と広報写真部門の組み写真で特選に選ばれ、全国広報コンクールに推薦されました。
まちの話題やイベント、地域活動に尽力している方々を積極的に取り上げ、全ての世代に分かりやすく、興味を持ってもらえる広報誌づくりをはじめ、ホームページやSNSなど、多様な媒体を活用した情報発信に努めてまいります。
-12月議会以降の主な取組-
それでは、12月議会以降の主な取組について御報告申し上げます。
今後の市政運営を総合的かつ計画的に進めていく上で、最上位の計画となる「第3次鹿屋市総合計画」については、総合計画審議会での議論を踏まえるとともに、各種団体との意見交換やパブリックコメントなどに基づいて計画案を取りまとめ、基本構想を本定例会に提案しております。
本市の農業振興の基礎となる「地域計画」については、目標地図を含めた素案の公告・縦覧を完了しました。
今後は「地域計画」に基づき、多様な担い手への農地の集積・集約を図ってまいります。
このほか、こども施策を総合的に推進するための基本方針を定める「鹿屋市こども計画」や「鹿屋市有機農業推進方針」「鹿屋市シティプロモーション戦略」などについても、本年度中の策定に向けて作業を進めております。
「湯遊ランドあいら」については、老朽化への対応や家族風呂の設置のほか、太陽熱温水設備などを備えた脱炭素のシンボル的な施設として、4月のリニューアルオープンに向けて整備しております。
吾平地域の中心拠点施設として、施設を活用した環境学習やスポーツ合宿の誘致、町内イベントとの連携について、指定管理者や事業者、団体等と協議を重ねながら、市内外から多くの方々に利用いただけるよう、準備を進めてまいります。
学校周辺における安全確保については、関係団体等からの意見聴取を行ったほか、通学路などの道路照明や街路灯、防犯灯の設置状況、夜間の照度、路面標示の現況について調査を実施しました。
海上自衛隊鹿屋航空基地については、施設の建替や改修など、自衛隊施設の強靭化を目的とした最適化事業が進められています。
本事業の展開にあたっては、地元企業の積極的な活用や受注機会の拡大など、地域経済の活性化につながるよう、国に対して積極的に働きかけてまいります。
また、今後予定されている鹿屋航空基地史料館の改修工事についても、本市の歴史や文化、魅力を発信できる施設となるよう提案してまいります。
高病原性鳥インフルエンザについては、これまで本市での発生はありませんが、年末から年始にかけて、出水市と霧島市において計3例が発生しました。
既に県内の移動制限等は全て解除されていますが、全国における1月の発生件数は過去最多となっていることから、肝属家畜保健衛生所などの関係機関と連携しながら、引き続き、防疫対策に万全を期してまいります。
-市政運営の基本方針-
国は、令和7年度の経済財政運営において、引き続き、賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済を実現し「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実なものとすることを、目指すこととしています。
最低賃金の引上げや価格転嫁等の取引適正化、人手不足に対応する省力化・デジタル化への投資促進や、生産年齢人口の減少を踏まえた労働市場改革に取り組むほか、地方創生2.0、防災・減災及び国土強靱化をはじめとする総合経済対策を推進することとしています。
令和7年度は、本定例会に提案しております市民と行政の協働によるまちづくりの指針となる「第3次鹿屋市総合計画」をスタートする年です。
社会経済情勢や国・県等の動向を注視しながら、市民や事業者の皆様とともに「ひと」と「まち」が元気で、市民一人ひとりが幸せを実感できる「健康都市かのや」の実現を目指してまいります。
初年度となる令和7年度は、
- 人口減少への対応
- 魅力ある産業・雇用による活性化
- 子ども・若者に住みよいまち
- 幸せを実感できる社会の実現
- シビックプライドの醸成
の5つを重点項目に掲げ、先行的・積極的な取組を進めてまいります。
1つ目は「人口減少への対応」です。
本市の合計特殊出生率は全国平均より高い水準にあるものの、平成26年に1,100人を超えていた出生数は年々減少し、昨年は700人を下回りました。
一方、平成26年に1,200人程度だった死亡数は昨年1,500人を超え、自然減が年々拡大する傾向にあります。
このため、若者の人生設計や出会い・結婚に向けた支援をはじめ、子育て支援策の更なる充実や移住就業支援金の創設など、実効性のある施策を展開してまいります。
また、人口減少と少子高齢化が進む中にあっても、住み慣れた地域で快適な生活を送るため、立地適正化計画に基づく誘導区域等への移住・定住の促進をはじめ、空き家の利活用や、デマンド交通のエリア拡大、都市基盤の整備、災害に強いまちづくりなど、日常生活における利便性と安全性の確保に取り組んでまいります。
併せて、労働人口の減少や高齢化が進行する中で、デジタル技術を積極的に活用し、生産性の向上や地域経済の活性化、行政サービスの向上など、誰もがデジタル化の恩恵を享受できる社会の実現に取り組んでまいります。
2つ目は「魅力ある産業・雇用による活性化」です。
世界的な食料情勢の変化や気候変動の影響、人口減少による農業構造の変化などを背景に、「食料・農業・農村基本法」が改正され、環境と調和のとれた食料システムの確立、農業の持続的な発展のための生産性の向上、農村における地域社会の維持等を図ることが求められています。
基幹産業として維持・発展してきた農林水産業を更に成長させるため、多様な担い手の確保・育成をはじめ、生産基盤の強化や環境保全型農業の推進、鳥獣被害対策の強化など、第2次かのや農業・農村戦略ビジョンに基づく取組を推進してまいります。
併せて、森林の適正管理や再造林を推進するとともに、水産業の経営基盤の強化を支援し、魅力ある農林水産業の振興を図ってまいります。
若者や女性にとって魅力的な雇用の場を創っていくためには、賃金の上昇や働き方改革による労働生産性の向上など、魅力ある働き方・職場づくりを官民連携で進めることが重要です。
地元企業における女性活躍の推進や働きやすい環境整備を促進するほか、従業員の奨学金返還を支援する制度の創設や、地元就職支援など、商工業の活性化と定住人口の増加を図る取組を推進してまいります。
また、県や関係機関と連携しながら、県農業開発総合センター大隅支場跡地への企業誘致や既存立地企業の事業拡大などを促進し、地域経済の活性化につなげてまいります。
3つ目は「子ども・若者に住みよいまち」です。
少子化や核家族化、保護者の就労状況の多様化など、社会の変化に伴い、こども・若者や子育て世帯を取り巻く環境は複雑化しています。
妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援や5歳児健診の実施、こどもの預け先の体制強化など、全てのこども・若者が幸福な生活を送ることができる社会の実現に向けた取組を総合的に推進してまいります。
また、将来の予測が困難な時代において、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となる資質・能力の育成と、人とのつながり、協働によって得られる幸せや生きがいを向上させていくことが求められています。
質の高い教育や社会教育等の充実を通じて、未来を創る心豊かでたくましい人材の育成に努めてまいります。
4つ目は「幸せを実感できる社会の実現」です。
今年は団塊の世代の方々が全て75歳以上となり、本市の5人に1人が後期高齢者になる見通しです。
少子高齢化による担い手不足や地域のつながりの希薄化などに伴い、地域を支えてきたコミュニティの重要性が増しており、その在り方を再検討する必要があります。
地域住民同士の対話を促し、住民主体による地域づくりの意識を醸成することで、互いに支え合いながら、自分らしく活躍できる地域づくりに取り組んでまいります。
生涯にわたって心身ともに健康で活躍できる社会の実現に向けて、健康に対する若い年代からの意識づけや特定健診、長寿健診の受診率の向上等に取り組んでまいります。
また、全ての人が生きがいを感じられ、多様性が尊重される社会を築いていくために、関係機関等と連携を図りながら、人権教育・啓発や男女共同参画の推進などに取り組んでまいります。
併せて、本市の豊かな自然環境を未来のこどもたちに引き継ぐため、脱炭素につながる取組の啓発や再生可能エネルギーの導入に対する支援など、市民、事業者、行政が一体となって脱炭素社会の実現に向けた取組を推進してまいります。
5つ目は「シビックプライドの醸成」です。
本市には、このまちを我が故郷として誇りに思い、イベントやまちづくりなど様々な分野で地域活動に積極的に参加し、地域を盛り上げている人がたくさんいらっしゃいます。
市民の皆様との対話を重視し、地域の持つ魅力を改めて掘り起こすとともに、地域に対する誇りや自負心を持ち、地域づくりにいきいきと活動する「活動人口」を増やす仕組みづくりに取り組み、市民の皆様とともにこれからのまちづくりを進めてまいります。
今年は、太平洋戦争の終結から80年の節目の年となります。
本市で開催している3つの戦没者追悼式の合同開催や、鹿屋の戦争や当時の暮らしに焦点をあてた特別企画展の開催など、戦没者を追悼し、平和を祈念するとともに、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代へ継承する戦後80年事業に取り組んでまいります。
来年1月には市制施行20周年を迎えます。
これまでの歩みを振り返るとともに、市民相互の一体感と鹿屋への誇りと愛着を高める契機となるよう、一人でも多くの方に参加いただき、市制施行20周年記念事業に取り組んでまいります。
-予算編成の考え方-
次に、予算編成の考え方について、申し上げます。
令和7年度当初予算は、将来にわたり持続可能で強固な財政構造の構築を目指す、鹿屋市行財政将来ビジョンの視点を念頭に置きつつ、限られた資源を選択と集中により効果的に活用し、本議会に提案しております第3次鹿屋市総合計画の5つの基本目標に基づく施策・事業を着実かつ積極的に推進する予算として編成しました。
その結果、令和7年度一般会計当初予算案の総額は、646億7千万円となり、前年度当初予算額と比べますと、5.9%の増で、過去最大の規模となりました。
歳入については、地方交付税や国庫支出金が増加するとともに、市税は定額減税終了による個人市民税の増額等を見込み1.8%・約2億1千万円の増となりました。
自主財源比率は、国庫支出金の増などを受け、前年度比1.2ポイント減の35.1%となっています。
歳出予算を性質別に見ますと「障害福祉サービス等給付費」や「児童手当費」の増により、扶助費が前年度比で約18億1千万円の増となり、扶助費を含む義務的経費は前年度比で約22億5千万円の増となりました。
また、普通建設事業費については、長寿命化計画に基づく小・中学校施設校舎改修工事や文化会館の改修工事、平和市営住宅改善工事のほか、排水路整備事業や道路メンテナンス事業など、インフラ整備の増により約2億5千万円の増となっています。
歳出予算を目的別に見ますと、性質別経費と同様に扶助費の増により、民生費が約20億8千万円増加し、歳出全体の41.7%を占めています。
「市債」については普通建設事業費の増などにより、発行額が前年度比で約8億円の増となっています。
「市債」と「基金」については、これまで、歳入・歳出両面にわたる行財政改革を積み重ねてきた結果、市債残高の縮減や一定の基金残高の確保など、健全財政を堅持しているところであり、今後も歳入の確保、歳出の削減はもとより、組織改革やデジタル化の推進など行財政全般にわたる取組を進めてまいります。
次に、特別会計及び公営企業会計当初予算案について、主なものを申し上げます。
国民健康保険事業特別会計予算については、110億5千300万円で、4.8%の減となりました。
主な要因は、被保険者数の減少に伴う、医療費など保険給付費の減によるものです。
後期高齢者医療特別会計予算については、16億8千800万円で、3.3%の増となりました。
これは、被保険者数の増加に伴う、広域連合納付金の増などによるものです。
介護保険事業特別会計予算については、116億4千100万円で、0.4%の増となりました。
これは、地域密着型介護サービス費の増加に伴う保険給付費の増などによるものです。
水道事業会計予算については、収益的収入は、16億9千749万4千円、収益的支出は、16億4千38万9千円で、資本的収入は、3千568万円、資本的支出は、12億201万6千円となりました。
主な事業として、耐用年数を超過した馬掛ポンプ場の更新を行うとともに、老朽管の布設替えなどについても、計画的に取り組んでまいります。
下水道事業会計予算については、収益的収入は、9億1千598万3千円、収益的支出は、8億6千56万9千円で、資本的収入は、4億3千944万4千円、資本的支出は、7億5千349万8千円となりました。
主な事業として、未整備地区の汚水管渠整備や、王子札元地区の道路冠水解消に向けて、雨水管渠整備を進めてまいります。
-主要施策の概要-
それでは、主要施策の概要について、現在策定中の第3次鹿屋市総合計画に掲げる5つの基本目標ごとに、新規及び拡充した事業を中心に御説明申し上げます。
基本目標1の「やってみたい仕事が広がるまち」では、第2次かのや農業・農村戦略ビジョン等に基づく農林水産業の振興や、商工業の活性化、雇用の促進に取り組みます。
「農業の生産基盤の強化」については、農産物の安定的な生産と農家所得の向上を図るため、地域計画に位置付けられ、規模拡大等を行う認定農業者や認定新規就農者に対して、国県補助の対象とならない農業用機械の導入や施設の整備を市単独で助成します。
「果樹産地づくり支援」については、アボカド等の希少性果樹の国産化へのニーズが高まっていることから、生産拡大に意欲的に取り組む農業者組織に対し、種苗や資材等の経費に対する助成を行います。
「青果用さつまいもの栽培技術・品質向上」については「日本さつまいもサミット」への出品に向けて、スマート農業の先端技術等と組み合わせた反収や品質の向上、貯蔵管理の徹底による高品質栽培に取り組む事業者を支援します。
「鳥獣被害対策の強化」については、有害鳥獣による被害軽減に総合的に取り組むため、捕獲情報や生息エリア等を見える化するアプリを導入するほか、捕獲報償金の市単独分の一部を引き上げます。
「環境に配慮した農業の推進」については、有機農作物の栽培技術の向上と生産拡大を図るため、実証展示ほを設置し、講習会を開催するほか、有機農作物の学校給食への供給に向けた取組を検討します。
「畜産施設における臭気対策」については、本年度実施した臭気調査や分析結果を基に、農家への現地指導や臭気軽減に関する農家指導マニュアルを作成するなど、環境改善に向けた取組を強化します。
「まもり・育てる林業の推進」については、次世代へつなぐ森林づくりに向けて、森林の適正な管理と再造林を推進するため、私有林の再造林、下刈り、除・間伐に係る市補助金を拡大し、森林所有者の負担軽減を図ります。
「魅力ある水産業の推進」については、カンパチ等の国内外の販路拡大と養殖業者の所得向上に向けて、冷凍フィレやロイン等の生産量の増加や作業の効率化を図るため、国の補助事業を活用し、市漁協が整備する急速凍結機の費用の一部を助成します。
「企業誘致等の推進」については、早期の産業用地整備に向けて、全国の企業へ向けた企業立地意向調査を実施するほか、専門家を活用した体制の強化を図るとともに、県や関係機関と連携した取組を進めます。
「若者就労支援」については、企業と市が一体となり、若者の地元企業への就職を促すため、奨学金の代理返還制度を利用する事業者への補助制度を創設します。
また、地元就職率の向上を図るため、市内の高校生が市内企業のPR動画を制作することで、市内企業を知っていただくとともに、地元で働くことへの理解を深める取組を新たに実施します。
基本目標2の「交流で賑わうまち」では、地域資源を生かした観光振興、スポーツによる交流促進、本市の魅力を活用した移住・定住の促進に取り組みます。
「シティプロモーションの推進」については、食のまちとしての本市の認知度向上に努めるとともに「かのやカンパチロウ」誕生から10年を迎えるに当たり、記念イベント「カンパチロウフェス」を開催するなど、積極的なシティプロモーションを展開します。
「観光分野における広域・官民連携の強化」については、本市への誘客促進による地域の活性化を図るため、貸切バスや高速船を利用した団体旅行商品を企画・販売する旅行業者に対して、補助金を交付します。
「魅力ある観光地の形成」については、輝北うわば公園において、キャンプ飯コンテストなど新たなイベントを通じて魅力を発信するほか、地域住民や専門家等を交え、中長期的な活性化方針を策定します。
大塚山公園の有効活用による串良地域の活性化を図るため、地域住民や団体、専門家を交えたプロジェクトチームによる検討会を開催し、大塚山公園の利活用策について検討します。
黒羽子観光農園の活性化を図るため、本年度策定した黒羽子観光農園活性化基本計画に基づき、地域おこし協力隊を採用するほか、新規品目導入支援等に取り組みます。
古江地区の地域資源を活用して、地域が主体となって活性化を探るための検討会や、海釣り体験などの実証イベントを開催する取組を支援します。
「スポーツ合宿・大会の推進」については、交流人口の増加と地域経済の活性化を図るため、スポーツ合宿等誘致推進奨励金の対象範囲を拡大するほか、各種競技団体や鹿屋体育大学等と連携し、大会の開催や合宿等の誘致を推進します。
「スポーツ施設の整備」については、市民や合宿者が安心して利用できるスポーツ環境の充実を図るとともに、本年11月に完成を予定している野里運動施設のこけら落としイベントを開催します。
「移住就業支援制度の充実」については、東京23区を除く県外から本市へ移住し、就業や起業された方などを対象に、最大で100万円の新たな支援金制度を創設します。
「シビックプライドの醸成」については、戦後80年を迎えるに当たり、戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代へつなぐため、当時の人々の暮らしに焦点を当てた特別企画展の開催や、創作演劇などを実施します。
また、令和7年度については、それぞれ開催している3つの戦没者追悼式を、合同で開催することとしています。
市制施行20周年記念事業については、来年1月に20周年を迎えることから、市民が主役の明るい未来の実現に向けた取組を推進するため、記念式典の開催やC&Kによる凱旋ライブのほか、一年を通じて各種冠事業を実施します。
また、複数年にわたる事業として、市史編さんの準備作業に入ります。
基本目標3の「こども・若者の未来を創るまち」では、こどもを産み育てやすい環境づくりや、未来を担う心豊かでたくましい人づくりのための教育の充実に取り組みます。
「子育て家庭支援策の充実」については、育児用品購入助成券の交付額を、第2子は6千円、第3子以降は1万2千円増額します。
また、子育て家庭の経済的な負担の軽減を図るため、病児保育を無償化します。
「乳児等通園支援事業」については、時間単位で保育所等を利用できる「こども誰でも通園制度」に、令和8年度の国の制度開始に先駆けて試行的に取り組みます。
「子ども医療費」については、こどもの健康増進と健やかな育成を図るため、これまで非課税世帯に限られていた現物給付方式を、18歳までの全てのこどもに拡大し、窓口負担を無くします。
「産後ケアの無償化」については、退院後の母子を対象に、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を行う、産後ケア事業の利用者負担分を助成します。
「地域全体で支える環境の整備」については、子育ての手伝いを頼みたい人と手伝いをしたい人がそれぞれ会員となり、子育ての助け合いを行うファミリー・サポート・センター事業の利用料を無償化します。
「若者の自立支援の充実」については、結婚・出産・育児を望む若者の出会いや結婚を支援するため、若手社会人を対象に、結婚・子育て等のライフプランセミナーと交流会を実施するほか、メタバース上での婚活イベントなどを開催します。
「豊かな心と健やかな体を育む教育の推進」については、家庭教育の理解促進や誰もが子育てしやすい環境を整えるため、家庭教育アドバイザーとサポーターを設置し、各地域でのサロン活動や健診会場での啓発活動等を行います。
「地域特性を生かした教育の推進」については、英語教育の推進と主体的に行動できる人材の育成を図るため、英語暗唱弁論大会を開催するほか、国立台北教育大学との連携協定に基づき新たな協定校を追加し、より多くの児童・生徒が英語を通じて交流する機会を創出します。
基本目標4の「安心して暮らし続けられるまち」では、快適な住環境の整備や防犯・交通安全など安心して暮らせる地域づくり、自然環境にやさしいまちづくりに取り組みます。
「持続可能な公共交通の構築」については、市民の移動手段の確保や利便性の向上を図るため、串良地域におけるくるりんバスを廃止し、乗合ワゴンによるデマンド交通の運行を開始します。
「デジタル基盤の活用」については、町内会による広報誌の配布回数を月2回から1回へ見直すことに併せて、本市の様々な旬な情報を伝える広報誌を、スマートフォンやタブレットで読みやすく表示し、市民がタイムリーに情報を共有できる環境の整備に取り組みます。
「防災・消防対策の充実」については、南海トラフ地震を見据えた防災意識の向上と家屋の耐震化を推進するため、建築士等による家具等の転倒防止指導や耐震支援制度等の学習会を開催するとともに、住宅の耐震改修に対する支援を引き続き行います。
「上下水道のインフラ対策」については、施設や基幹管路の耐震化と老朽化に伴う整備を行うとともに、本年度実施した、衛星を活用した漏水調査に基づく漏水修繕や布設替工事に取り組みます。
「防犯・交通安全の推進」については、交通事故の防止や児童・生徒の通学等における安全を確保するため、学校周辺の照明が少なく暗い場所に通学路灯を新たに設置するほか、区画線等の路面標示などの補修に、計画的に取り組みます。
「ゼロカーボンシティかのやの推進」については、本年4月にリニューアルオープンする湯遊ランドあいらにおいて、親子体験型脱炭素教室など児童向けの環境学習を開催します。
また、二酸化炭素排出量を削減するため、市の公共施設5か所に太陽光発電設備を設置し、再生可能エネルギーの導入を推進するとともに、引き続き、個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入の支援を行います。
「ごみ減量・リサイクルの推進」については、市民と行政とが一体となったきれいなまちづくりを推進するため、市と町内会が連携し、違反ごみが多いごみステーションを中心に、違反ごみの回収・処分等を実施するとともに、適切な分別方法の啓発を強化します。
基本目標5の「ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち」では、こどもから高齢者、障がいのある人など多様な地域住民が互いに支えあいながら、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる「地域共生社会」の実現に取り組みます。
「高齢者福祉の充実」については、高齢者の健康づくりや社会参加活動等の促進を図るため、高齢者元気度アップ・ポイント事業等において、スマートフォンでポイント管理や活動履歴を確認できるアプリを導入します。
「介護予防の推進と高齢者の生きがいづくり」については、高齢者の健康保持と福祉の増進を図るため「公衆浴場利用券」「はり・きゅう施術料助成券」「敬老バス乗車賃助成」の3つの事業を統合し、新たに使い道を拡充した共通券を、特定健診や長寿検診の受診者を対象に交付します。
「健康寿命の延伸」については、接種率向上を通じた疾病の発症や重症化の予防を図るため、4月から新たに予防接種法上の定期接種に位置付けられた帯状疱疹ワクチン予防接種費用の一部を助成します。
「健康増進のための野菜摂取量の『見える化』」については、生活習慣病予防による健康寿命の延伸を図るため、イベント等において、野菜摂取量評価機器を活用した測定会を実施し、市民の健康づくりに向けた意識啓発と習慣の改善につなげます。
「地域支援体制の充実」については、地域づくりの主体となる活動人口の増加を図るため、市民活動団体が行う地域活性化や課題解決に向けた取組を支援します。
「市政運営」では、厳しい社会情勢にあっても、更なる行財政改革の推進や時代に即した簡素で効率的な組織機構の整備などを一層推進し、安定した市政運営を図ります。
「デジタル・ガバメントの推進」については、国が示す移行対象20業務について、令和7年度末までに、ガバメントクラウド等を活用した標準準拠システムへ移行する必要があることから、円滑な移行に向けた取組を進めます。
税証明及び収納窓口の業務を一本化して民間委託し、業務効率化を図ります。
また、法務局からの登記済通知書等を電子化し、情報連携の効率化と「行かない市役所」の実現を目指します。
「戸籍の振り仮名対応」については、戸籍法の一部改正により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることから、本市に本籍をおく全ての世帯に対し、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知し確認を行うなど、適切な対応に努めます。
「生成AI等の導入」については、様々な分野で活用されていることから、自治体業務への段階的な導入を見据え、対象業務の調査や職員研修などの取組を進めます。
「AI入所選考システム導入による業務効率化」については、業務の効率化と入所選考期間の短縮による市民サービスの向上を図るため、保育所等の入所選考事務にAIによる利用調整システムを導入します。
「地域おこし協力隊の活用」については、本市のPRや基幹産業の活性化につながる活動などを行いながら、任期満了後の定住・定着を目指す隊員4名を採用する予定です。
本年4月の「組織機構の改正等」については、本市の重要施策を推進するために行うものです。
老朽化した公共施設の統廃合や未利用の土地・建物の売却、有効活用を図るとともに、指定管理者制度を導入している公共施設や庁舎、公用車など、市が保有する財産の効率的な管理・運営に努めるため、総務部内に新たに「財産管理活用課」を設置し、重点的に取り組んでまいります。
また、喫緊の課題である空き家対策・活用を進めるため、市長公室地域活力推進課内に「空き家活用専任職員」を配置することとしています。
職員の人材育成については、少子高齢化に伴う人口減少やデジタル化の進展など、これまで以上に複雑で高度化する行政課題や市民ニーズに的確に対応するため、目指すべき職員像や人材育成の基本的な考え方等をまとめた「鹿屋市人材育成ビジョン」を本年3月に策定することとしています。
以上、主要な施策の概要について5つの基本目標ごとに御説明しました。
我が国の経済は、コロナ禍の影響から脱した後、企業収益が過去最高を更新するなど緩やかに回復している一方で、エネルギーや食料品の価格高騰により個人消費は力強さを欠いた状態が続くなど、依然として厳しい状況が続いています。
今後も、国・県と連携し、物価高騰対策や地域経済対策に取り組んでまいります。
次に、令和6年度一般会計補正予算案の概要について御説明申し上げます。
今回の補正予算は、国の補正予算に対応した事業のほか、各種基金への積立、事業費の確定に伴う減額等を中心に編成しました。
補正予算の総額は、13億2千598万7千円で、補正後の予算額は672億6千218万3千円となり、前年度同期と比べ、23億9千995万2千円、3.7%の増となります。
それでは、主な事業について、御説明申し上げます。
「障がい福祉施設物価高騰対策事業」及び「介護保険施設等物価高騰対策事業」については、国が定める公的価格等により運営し、物価高騰の影響を受けている、障がい福祉サービス事業所及び介護サービス事業所の、LPガス及び食材費等の価格高騰分の一部を支援するものです。
「県営土地改良事業負担金」については、県が実施している土地改良事業について、計画期間内の完成に向け事業量を拡大することに伴い、市負担金に変更が生じることから、必要額を予算計上するものです。
「障害福祉サービス等給付費」については、障害福祉サービス等の算定の基礎となる報酬の改定や、利用件数の増に伴い、障害福祉サービス費等の不足額を計上するものです。
-条例その他の案件について-
次に、議案第15号から第33号までの条例その他の議案について、その主なものを御説明申し上げます。
議案第19号については、印鑑登録証明書を請求する際の手続を見直すほか、印鑑登録の性別欄を廃止するものです。
議案第21号については、子ども・子育て支援法等の一部改正により、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度」が創設されたことに伴い、施設の設備及び運営の基準を条例で定めるものです。
議案第25号については、新たに鹿屋市高齢者福祉共通券交付事業を開始するものです。
本事業は、利用できるサービスを拡充した共通券を、特定健診等の受診者に交付し、高齢者の健康意識の向上や生きがいづくりの充実を図るものです。
議案第27号については、市営住宅の入居促進を図るため、収入認定月額を改正し、入居要件を緩和するものです。
議案第31号については、市政の総合的な経営指針となる第3次鹿屋市総合計画の基本構想を策定するものです。
以上、市政運営に関する私の所信の一端を申し上げ、今回提案しております主な議案等について御説明しました。よろしく御審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
- 施政方針(令和7年3月鹿屋市議会定例会令和7年2月19日)
- 施政方針(令和6年3月鹿屋市議会定例会令和6年2月21日)
- 施政方針(令和5年3月鹿屋市議会定例会令和5年2月22日)
- 所信表明 (令和4年3月鹿屋市議会定例会 令和4年2月24日)
- 施政方針 (令和3年3月鹿屋市議会定例会 令和3年2月25日)
- 施政方針(令和2年3月鹿屋市議会定例会令和2年2月19日)
- 所信表明(平成30年3月鹿屋市議会定例会 平成30年2月28日)
- 施政方針(平成31年3月鹿屋市議会定例会平成31年2月21日)
- 施政方針(平成27年3月鹿屋市議会定例会平成27年2月19日)
- 施政方針(平成28年3月鹿屋市議会定例会平成28年2月25日)
- 施政方針(平成29年3月鹿屋市議会定例会平成29年2月23日)
- 施政方針(平成26年6月鹿屋市議会定例会平成26年6月6日)
- 所信表明(平成26年3月鹿屋市議会定例会平成25年2月27日)
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.
 文字サイズ
文字サイズ