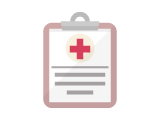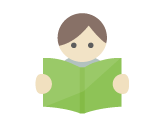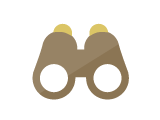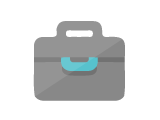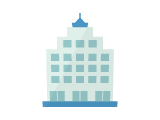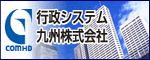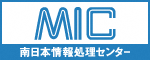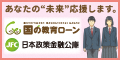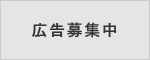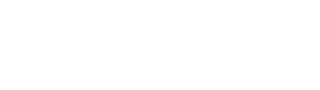更新日:2024年12月4日
ここから本文です。
ランピースキン病
令和6年11月6日、福岡県の乳用牛農場において、国内初となるランピースキン病の発生が確認されました。畜産農家の皆様におかれましては、飼養衛生管理を徹底し、本市での発生阻止及びまん延防止に努めましょう。
国内における発生状況
ランピースキン病に関する情報(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)
ランピースキン病とは
- ランピースキン病ウイルスにより起こる感染症
- 牛・水牛に皮膚の結節や水腫,発熱,泌乳量の低下等、多様な症状を示す病気
- 主に蚊、サシバエ、ヌカカ等の吸血昆虫(ベクター)による機械的伝搬により感染
- 汚染された飼料、水、器具を介しての感染もみられる
- 近年アジア全域で感染が拡大しており、日本では本年11月に福岡県で初発
- 発症牛の早期発見、隔離、ワクチン接種等による総合的な防疫対策が重要
- 人への感染の心配はありません
侵入防止対策
毎日の健康観察の徹底
- 飼養牛の定期的な観察及び早期発見
→症状:全身の皮膚の結節や水腫、発熱、泌乳量の低下等
本病を疑う症状がみられた場合、獣医師又は家畜保健衛生所への早期通報をお願いします。 - 感染が疑われる牛の早期隔離
→農場内での感染防止
外部からのウイルス持ち込み防止のため、導入牛も隔離飼育をお願いします。 - 出荷等により農場外へ牛を移動させる場合の健康状態の確認
→牛の移動による伝染病のまん延防止
吸血昆虫対策
- 殺虫剤の散布等による吸血昆虫(蚊、サシバエ、ヌカカ等)対策
→吸血昆虫によるウイルスの機械的伝播防止
飼養器具等の取扱
- 飼養器具の消毒の徹底,他の農場で飼養された飼養器具の原則持ち込み防止
→ウイルスが付着した飼養器具等の持ち込みが感染の原因となるおそれがあります。
診療,家畜人工授精等の注意点
- 注射針、人工授精用器具等を使用する際は、1頭ごとに確実に交換又は消毒を実施
→血液によるウイルスの伝播防止
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.
 文字サイズ
文字サイズ