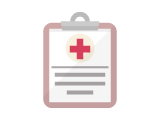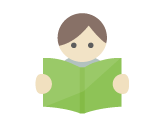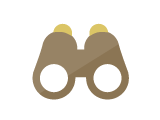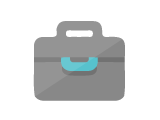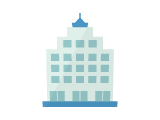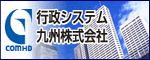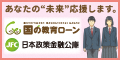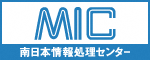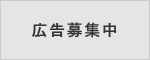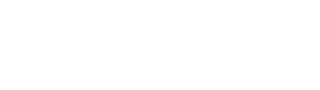更新日:2025年8月12日
ここから本文です。
後期高齢者医療制度
- 後期高齢者医療制度のしくみ
- 対象者
- 自己負担割合及び自己負担限度額・食事代
- 「限度額適用認定」及び「限度額適用・標準負担額減額認定」
- 後期高齢者医療保険の保健事業
- ガイドブック(PDF:3,792KB)
後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で運営しており、鹿児島県内すべての市町村が加入し、鹿児島県後期高齢者医療広域連合が運営しています。
- 広域連合の役割:後期高齢者医療制度の運営主体として、保険料の決定、医療の給付などを行います。
- 市町村の役割:後期高齢者医療保険の申請受付、保険料の徴収、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。
医療費全体の1割または2割(現役並み所得者は3割)を後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)が自己負担し、残りは公費(国、県、市町村)から約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)から約4割、後期高齢者医療保険料から約1割で賄われています。
参考:鹿児島県後期高齢者医療広域連合HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
対象者
後期高齢者医療保険の対象となる方は、
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳で一定の障がいのある方で、申請により障害認定を受けている方
障害認定について
65歳から74歳で次の障がいの程度に該当する場合、証明書類を添えて窓口で申請し、認定を受けることで、後期高齢者医療の被保険者となることができます。
|
証明書類 |
障がいの程度 |
|---|---|
|
身体障害者手帳 |
1級、2級、3級及び4級の一部 |
|
精神障害者保健福祉手帳 |
1級、2級 |
|
療育手帳 |
A1、A2 |
|
国民年金証書 |
1級、2級(障害年金) |
65歳から74歳で一定の障がいのある方が、被保険者になったあとで保険料や給付について十分考慮の上、いつでも取り下げることができます。(日付を遡って手続きすることはできません。)
自己負担割合及び自己負担限度額・食事代
被保険者の個人及び世帯の所得に応じて、医療機関にかかるときの自己負担割合などは変わります。
自己負担割合をクリックすると、自己負担限度額や食事代等の説明箇所へリンクします。
| 自己負担割合 | 所得区分 | |
|---|---|---|
| 3割 |
現役並み所得者 |
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方※次の(1)~(3)の要件に該当する場合、申請により1割または2割負担となります。 (1)同じ世帯に被保険者が1人で、その方の収入が383万円未満の方 (2)同じ世帯に被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満の方 (3)同じ世帯に70歳~74歳の人と被保険者が1人の場合70歳~74歳の人と被保険者の収入合計額が520万円未満の方 |
| 2割 | 一般Ⅱ |
同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、次の(1)または(2)に該当する方 (1)同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 (2)同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 |
| 1割 | 一般Ⅰ |
「現役並み所得者」、「一般Ⅱ」、「低所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」以外の方 昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者及びその世帯の被保険者で、住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいても、被保険者の旧ただし書き所得(総所得から基礎控除額を差し引いた額)の合計額が210万円以下の方 |
| 低所得者Ⅱ | 同じ世帯の全員が住民税非課税である方(低所得者Ⅰ以外の方) | |
| 低所得者Ⅰ | 同じ世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額(年金の所得は控除額を80万6千7百円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方 | |
3割負担の方
【自己負担限度額(月額)・食事代】
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 1食当たりの食費(標準負担額) |
療養病床を利用時の 食費・居住費(注3) |
|
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人単位)/外来+入院(世帯単位) | ||||
|
現役並みⅢ (課税所得が690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円(注1)> |
510円(注2) |
1日当たり
(難病患者は0円)
|
|
|
現役並みⅡ (課税所得が380万円以上) |
限度額適用認定 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円(注1)> |
||
|
現役並みⅠ (課税所得が145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円(注1)> |
|||
注1:多数回該当<過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当>の場合の限度額です。
注2:国指定の難病患者等の負担額は、300円です。
注3:入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の食費は、入院時食事代の標準負担額と同額になります。
2割負担の方
【自己負担限度額(月額)・食事代】
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 1食当たりの食費(標準負担額) | 療養病床を利用時の食費・居住費(注4) | |
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人) | 外来+入院(世帯) | |||
| 一般Ⅱ |
18,000円または6,000円+(医療費(注1)-30,000円)×10%の低い方 <年間上限144,000円> |
57,600円<44,400円(注2)> | 510円(注3) |
1日当たり
(難病患者は0円) |
注1:医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
注2:多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当)の場合の限度額です。
注3:国指定の難病者の負担額は、300円です。
注4:入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の食費は、入院時食事代の標準負担額と同額になります。
1割負担の方
【自己負担限度額(月額)・食事代】
|
所得区分 |
自己負担限度額(月額) | 1食当たりの食費(標準負担額) | 療養病床を利用時の食費・居住費(注5) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
外来(個人) |
外来+入院(世帯) | |||||
| 一般Ⅰ | 18,000円(注1) |
57,600円 <44,400円(注2)> |
510円(注3) |
1日当たり
|
||
| 低所得者Ⅱ | 限度額適用・標準負担額減額認定 | 8,000円(注1) | 24,600円 |
90日までの入院240円 91日以降の入院190円(注4) |
1日当たり
|
|
| 低所得者Ⅰ | 15,000円 | 110円 |
1日当たり
老齢福祉年金受給者及び境界層該当者
|
|||
注1:1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額は、144,000円です。
注2:多数回該当<過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当>の場合の限度額です。
注3:国指定の難病者の負担額は、300円です。
注4:過去1年で90日を超える入院をした時には、来庁者の公的身分証明書及び入院日数が確認できるもの(領収証等)をご持参のうえ、申請をお願いします。後期高齢者医療制度以外の医療保険の日数を含む場合もあります。
注5:入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の食費は、入院時食事代の標準負担額と同額になります。(難病指定患者は0円)
「限度額適用認定」及び「限度額適用・標準負担額減額認定」について
※令和6年12月2日以降、認定証の新規発行が廃止になりました。資格確認書に限度区分を併記することで、認定証がなくても、限度区分の確認ができます(限度区分を併記するには申請が必要です)。
医療機関に、「現役並みⅠ・Ⅱ」に該当する方は「限度額適用認定証」を、「低所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示、又はマイナ保険証による受診をしていただくと、保険適用の医療費や食事代がそれぞれの区分の自己負担限度額までに、抑えることができます。
「限度額適用認定」及び「限度額適用・標準負担額減額認定」の交付を受けるには、申請が必要です。
申請に必要なもの
- 手続きに来られる方の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点)
- 委任状(別世帯の代理人が申請する場合)
後期高齢者医療制度の保健事業
人間ドック
お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。
|
事業名 |
内容等 |
必要なもの |
|---|---|---|
|
人間ドック利用助成事業 |
対象者:受診日現在、後期高齢者医療の被保険者 |
後期高齢者医療の保険証又は資格確認書 |
長寿健診
|
事業名 |
内容等 |
必要なもの |
|---|---|---|
|
長寿健診事業 |
対象者:後期高齢者医療の被保険者 |
長寿健診受診券 |
鹿児島県後期高齢者医療広域連合のサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.
 文字サイズ
文字サイズ