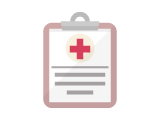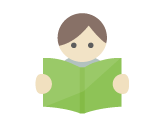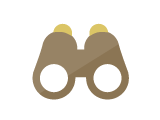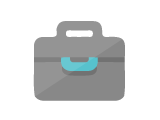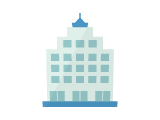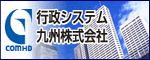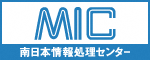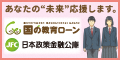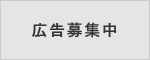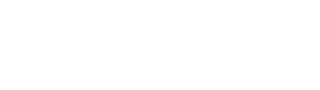更新日:2025年10月10日
ここから本文です。
国民年金
国民年金のしくみ
日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての方が国民年金に加入します。
つまり、厚生年金や共済組合などの加入者も、国民年金に加入していることになります。
国民年金には「老齢基礎年金」「遺族基礎年金」「障害基礎年金」の3種類の基礎年金があります。
厚生年金や共済年金は、この基礎年金に上乗せして支給されます。
第1号被保険者
| 加入する人 | 納付方法 |
|---|---|
| 自営業・自由業の人とその配偶者及び学生で、20歳以上60歳未満の方(厚生年金、共済組合加入者を除く) |
令和7年度保険料(月額)17,510円 日本年金機構から送付される納入通知書で金融機関(郵便局含む)かコンビニエンスストアまたは電子(キャッシュレス)決済で納めることができます。 |
第2号被保険者
| 加入する人 | 納付方法 |
|---|---|
| 厚生年金・共済組合加入者 |
厚生年金や共済組合から基礎年金に必要な費用として支払われます |
第3号被保険者
| 加入する人 | 納付方法 |
|---|---|
| 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方 | 保険料は厚生年金や共済組合が制度全体で負担します 個人で納める必要はありません |
国民年金の届出
以下の書類を準備し、手続きに必要なものをそろえてお越しください。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証や個人番号カードなど)
本人以外が手続きをする場合は、代理人であることがわかる書類(委任状など)
国民年金に加入するとき
| 加入する | 必要なもの |
|---|---|
| 会社を辞めたとき |
|
| 会社員である配偶者の扶養(健康保険)からはずれたとき |
|
| 任意加入するとき |
|
国民年金をやめるとき
| 国民年金をやめるとき | 必要なもの |
|---|---|
| 死亡したとき |
|
その他
| その他 | 必要なもの |
|---|---|
| 転入したとき |
|
| 保険料を納められないとき(免除申請、学生納付特例申請) |
|
| 年金を請求するとき |
|
老齢基礎年金
保険料を納めた期間や免除期間が原則として10年以上あると、65歳から老齢基礎年金が受けられます。
年金を受けとるためには、原則として最低10年(120月)必要です。(但し、受給資格期間10年は、平成29年8月からの施行)
老齢基礎年金額(令和7年度)831,700円
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間、すべての国民年金の保険料を納めた場合に満額が受けられます。
保険料を納めた期間が不足する場合は、不足期間に応じて減額されます。
資格期間
- 保険料を納めた期間(厚生年金・共済年金含む)
- 保険料の全額免除・学生納付特例・納付猶予制度を受けた期間
- 保険料の4分の3免除期間、半額免除期間、4分の1免除期間を納付した期間
- 第3号被保険者期間
国民年金の支給開始年齢は、原則65歳です。
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から75歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求できます。
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中に、初診日がある病気・けがで障がいの状態になったときに受けられます。
被保険者の資格を喪失したあとでも、60歳以上65歳未満の国民年金の繰り上げ支給をされていない方で、国内在住中に初診日がある病気・けがで障がいの状態になったときには受けられます。
また、20歳になる前に初診日がある場合には、一定の条件を満たせば20歳から障害基礎年金を受けることができます。
受給資格
受給資格は下記のすべてを満たすときに受けられます。
初めて診断を受けた日(初診日)の要件
障がいの原因となった病気・けがで診療を受けた最初の日(初診日)に、国民年金被保険者であるか、60歳以上65歳未満の国民年金被保険者であった方で日本国内に住所がある方。
障がいの状態の要件
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日か、1年6か月の間に治癒または症状が固定した日)の障害等級が1級か2級である方。
- 障害者手帳の等級とは異なります
保険料納付期間の要件
初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月までの国民年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除・学生納付特例・納付猶予期間を合わせた期間が3分の2以上である方。
または、令和18年3月31日までに、65歳未満の初診日があるときは、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない方。
障害基礎年金の額
令和7年度4月以降年金額
- 1級年額1,039,625円
- 2級年額831,700円
子の加算額
生計維持関係にあり、18歳到達の年度末までの子、または20歳未満の障害等級1・2級の子がある場合には、下記の加算額が受けられます。
加算額
- 1人目・2人目
各239,300円
- 3人目以降
各79,800円
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持していた子のある配偶者または子が受けられる年金です。
ここでいう子とは、18歳到達の年度末までの子、または20歳未満の障害等級1・2級の子をいいます。
受給資格は下記のとおりです。
- 国民年金に加入中の方
- 国民年金に加入していた方で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方
- 資格期間が25年以上ある老齢基礎年金の受給権者
- 老齢基礎年金の資格期間が25年以上ある方
1、2については、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済と保険料免除・学生納付特例・納付猶予期間を合わせた期間が3分の2以上である方。または令和8年3月31日以前に65歳未満の死亡日があるときには、死亡日の前日において、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない方。
遺族基礎年金の額
令和7年度4月以降年金額(年間831,700円の場合)
- 子が1人ある配偶者が受ける場合1,071,000円
- 子1人が受ける場合831,700円
子の加算額
子が2人以上いる場合には、下記の加算額が受けられます。
加算額
- 2人目
各239,300円
- 3人目以降
各79,800円
寡婦年金
寡婦年金は、第1号被保険者として10年以上保険料を納めた夫が死亡した場合に、夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合には支給されません。また妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合には支給されません。
年金額は、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金の額の4分の3になります。
死亡一時金
死亡一時金は、第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、障害基礎年金や老齢基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、死亡した方と生計を同じにしていた遺族に支給されます。
遺族の範囲は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
死亡一時金は、死亡から2年を経過すると、時効により請求できなくなります。
保険料納付済期間の月数と半額免除期間の月数の2分の1の月数とを合計した月数
36月以上180月未満
120,000円
180月以上240月未満
145,000円
240月以上300月未満
170,000円
300月以上360月未満
220,000円
360月以上420月未満
270,000円
420月以上
320,000円
保険料の免除制度
第1号被保険者で、経済的理由などにより保険料納付が困難な方(学生を除く)は、申請による免除制度があります。
老齢基礎年金をもらうとき、全額免除を受けた期間については、保険料を全額納付した場合の2分の1になり、半額免除を受けた期間は4分の3になります。
納付猶予制度
50歳未満(学生を除く)の第1号被保険者で、経済的理由などにより保険料納付が困難な方は、申請による猶予制度があります。
免除制度が世帯主の所得も審査するのに対し、納付猶予制度では、申請者及び配偶者の前年所得が一定以下の場合は、納付が猶予されます。
納付猶予期間は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。
学生納付特例制度
第1号被保険者で大学・短大・各種専門学校などの学生は、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請による学生納付特例制度があります。
学生納付特例期間は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。
保険料の追納制度
「免除」や「納付猶予」・「学生納付特例」制度を受けた期間については、10年以内に納めること(追納)ができます。
追納することにより老齢基礎年金額が増えます。
関連リンク
国民年金について、さらに詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.
 文字サイズ
文字サイズ