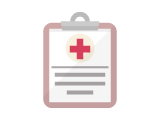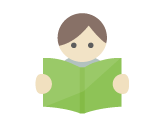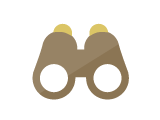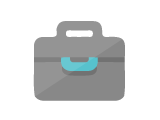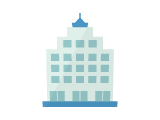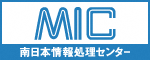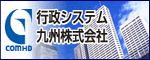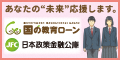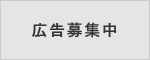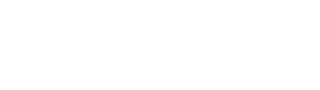更新日:2025年11月21日
ここから本文です。
国民健康保険の給付
- 病院にかかるとき(療養の給付)
- 入院したときの食事代
- 医療費が高額になったとき(高額療養費)
- 子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
- 亡くなられたとき(葬祭費)
- いったん医療費を全額自己負担したとき(療養の給付)
- 移送されたとき(移送費)
- 柔道整復師(整骨院、接骨院)や鍼灸(はり・きゅう)、あんま・マッサージの施術を受けるとき
- 交通事故などにあったとき(第三者行為による傷病)
- 厚生労働大臣指定の特定疾病
- 世帯外の方が手続きをする場合
お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。
※ここに掲げている70歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用を受けていない方のことです。
病院にかかるとき(療養の給付)
病気やケガで病院等にかかるとき、窓口でマイナ保険証や保険証(国民健康保険被保険者証)を提示することにより、医療費の一部を負担する(一部負担金)だけで診療を受けることができます。
一部負担金以外の医療費は、後で鹿屋市国民健康保険より病院等に支払われます。
|
年齢 |
自己負担 |
|
|---|---|---|
|
6歳に達する日以降の最初の3月31日まで |
2割 |
|
|
6歳に達する日以降の最初の4月1日から70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前日)まで |
3割 |
|
|
70歳の誕生月の翌月(1日生まれは誕生月)から75歳の誕生日の前日まで |
現役並み所得者以外 |
2割 |
|
現役並み所得者の方 |
3割 |
|
入院したときの食事代
入院中の食事代については、診療や薬にかかる費用とは別に、一部を自己負担してください。
残りの食事代は鹿屋市国民健康保険が負担します。
入院中の食事代の負担額は次のとおりです。
令和7年3月31日まで
|
区分 |
負担額(1食あたり) |
||
|---|---|---|---|
|
一般(下記以外の方) |
490円 |
||
|
住民税非課税の世帯に属する方 |
90日以内の入院 |
230円 |
|
|
90日を超える入院 |
180円 |
||
|
低所得1 |
110円 |
||
令和7年4月1日以降
|
区分 |
負担額(1食あたり) |
||
|---|---|---|---|
|
一般(下記以外の方) |
510円 |
||
|
住民税非課税の世帯に属する方 |
90日以内の入院 |
240円 |
|
|
90日を超える入院 |
190円 |
||
|
低所得1 |
110円 |
||
医療費が高額になったとき(高額療養費)
ひと月に医療機関で支払った一部負担金の額が世帯ごとに定められた額(自己負担限度額)を超えたとき、その超えた分が申請により払い戻されます。
高額療養費の計算は、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)などにより審査しますので、診療を受けた月から少なくとも3か月あとになります。(審査の結果、さらに数か月お待ちいただくことがあります。)
国保の給付対象とならない入院時の差額ベッド代や食事代、歯科等の自由診療は支給対象外です。
高額療養費支給申請の簡素化
次に該当する世帯を除き、一度申請することにより、次回以降の高額療養費は申請なしに自動振込で支給されます。
- 国民健康保険税の滞納が生じた場合
- 指定した金融機関の口座に高額療養費が振込できなくなった場合
- 申請の内容に偽りその他不正があった場合
- そのほか、市長が適当でないと認める場合
必要書類
- 本人確認書類
- 世帯主名義の口座の通帳
- 委任状(手続きされる方が世帯外の場合必要)
簡素化の対象とならない場合(条件等に当てはまらない場合)については医療機関の領収書が必要になります。
郵送での申請をご希望される場合は、国民健康保険係(0994-31-1162)へお問い合わせください。
高額療養費の自己負担限度額
同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
70歳未満の人
| 所得【※注1】要件 | 区分 | 限度額(A)(3回目【※注2】まで) | 限度額(A)(4回目【※注2】以降) |
|---|---|---|---|
| 所得金額901万円超 | (ア) | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 所得金額600万円超~901万円以下 | (イ) | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 所得金額210万円超~600万円以下 | (ウ) | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 所得金額210万円以下 | (エ) | 57,600円 | 44,400円 |
| 市民税非課税世帯 | (オ) | 35,400円 | 24,600円 |
注1:所得とは、国民健康保険税の算定基準となる「基礎控除後の所得金額等」のことです。
注2:同一世帯(国保加入者のみ)で、1年間(直近12か月)に診療費が「自己負担限度額」に達した回数
70歳以上の人
| 所得区分 | 外来の限度額(B)(個人単位) | 入院と外来を合算した限度額(C)(世帯単位) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | III.(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000)×1%(多数該当となる場合は、140,100円) | |
| II.(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000)×1%(多数該当となる場合は、93,000円) | ||
| I.(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000)×1%(多数該当となる場合は、44,400円) | ||
| 一般(課税所得145万円未満等) | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円(多数該当となる場合は、44,400円) | |
| 低所得者II(※注1) | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者I(※注2) | 8,000円 | 15,000円 | |
注1:低所得者IIとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人です。
注2:低所得者Iとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いたときに0円となる世帯に属する人です。
- 低所得者I・IIの人は、「国民健康保険限度額適用・食事療養(兼生活療養)標準負担額減額認定証」を、現役並み所得者I・IIの人は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。
認定証が必要な方は市役所で交付申請をしてください。
高額療養費の算出方法
70歳未満の人
同じ医療機関(※)で受けた診療などについて支払った保険診療の一部負担金(以下「一部負担金」という。)が「限度額(A)」を超えた場合その超えた額が支給されます。
ただし、医科・歯科別、入院・外来別等となります。
医療機関から交付された処方せんにより、薬局に薬代として支払った自己負担の額については、処方せんを交付した医療機関に支払った自己負担の額と合算して1件として高額療養費の計算ができます。
又、同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上の人
すべての医療機関で支払った一部負担金が計算の対象となります。次の順で計算します。
- 個人ごとに、外来すべての一部負担金の合計額が「外来の限度額(B)」を超えた場合、その超えた額が支給されます。
- 国保に加入している同じ世帯のすべての70歳以上の人の入院と外来の一部負担金の額を合計し、「入院と外来を合算した限度額(C)」を超えた額が支給されます。
70歳未満の人と70歳以上の人の合算
国保に加入している同じ世帯のすべての70歳未満の人の一部負担金(ただし、21,000円以上のもの)と70歳以上の人の一部負担金の額を合計し、「限度額(A)」を超えた額が支給されます。
75歳到達月における自己負担限度額の特例
月の途中で満75歳となる人は、その月だけ高額療養費の自己負担限度額が2分の1となります。
(後期高齢者医療制度も、満75歳となるその月だけ自己負担限度額が2分の1となります。)
限度額適用認定証、食事療養(兼生活療養)標準負担額減額認定証
医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示し、情報提供に同意することで、事前の手続きなく自己負担限度額を超える分の支払いが免除され、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。
ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は事前の手続きが必要となることがあります。
また、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合や、同一医療機関であっても外来と入院がある場合などは、後日、高額療養費の支給申請が必要となることがあります。
マイナ保険証をお持ちでない方、マイナ保険証で限度額の情報を確認できなかった方は、市役所の本庁や支所での申請が必要です。
【必要なもの】
- 来庁者の本人確認書類
マイナ保険証を利用することで、認定証の事前の手続きは不要となりますので、ぜひご利用ください。
ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は、事前の手続きが必要となることがあります。
- 限度額適用認定証・・・窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。
- 食事療養(兼生活療養)標準負担額減額認定証・・・入院したときの食事代が減額されます。
交付申請できる認定証
70歳未満の人
交付申請できる認定証は、所得区分に応じ下の表のとおりとなります。
| 所得区分 | 交付申請できる認定証 |
|---|---|
| 市民税非課税世帯以外の世帯 | 限度額適用認定証 |
| 市民税非課税世帯 | 限度額適用・食事療養(兼生活療養)標準負担額減額認定証 |
70歳以上の人
交付申請できる認定証は、所得区分に応じ下の表のとおりとなります。
| 所得区分 | 交付申請できる認定証 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | III.(課税所得690万円以上) | ありません |
| II.(課税所得380万円以上) | 限度額適用認定証 | |
| I.(課税所得145万円以上) | ||
| 一般(課税所得145万円未満等) | ありません | |
| 低所得者II | 限度額適用・食事療養(兼生活療養)標準負担額減額認定証 | |
| 低所得者I | ||
現役並み所得者IIIおよび一般の世帯の人については認定証はありませんが、医療機関に高齢受給者証を提示することで、窓口での支払い(保険適用分)は自己負担限度額までになります。
高額医療・高額介護合算について
この制度は医療と介護、両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減するものです。
医療保険からは「高額療養費」、介護保険からは「高額介護サービス費」として、自己負担限度額を超えた分については、支給されてきました。
その制度に加えて、医療保険と介護保険の自己負担額を世帯ごとに1年間(毎年8月から翌年7月31日)の合計をし、下記の基準額を超えた場合、その額を高額医療・高額介護合算療養費として支給する制度です。
70歳未満の方
|
所得要件 |
区分 |
医療保険+介護保険の自己負担限度額(年額) |
|---|---|---|
|
所得が901万円を超える |
(ア) |
212万円 |
|
所得が600万円を超え901万円以下 |
(イ) |
141万円 |
|
所得が210万円を超え600万円以下 |
(ウ) |
67万円 |
|
所得が210万円以下(住民税非課税世帯除く) |
(エ) |
60万円 |
|
住民税非課税世帯 |
(オ) |
34万円 |
70歳以上の方
|
所得区分 |
医療保険+介護保険の自己負担限度額(年額) |
|
|---|---|---|
|
現役並み所得者 |
III.(課税所得690万円以上) |
212万円 |
|
II.(課税所得380万円以上) |
141万円 |
|
|
I.(課税所得145万円以上) |
67万円 |
|
|
一般(課税所得145万円未満等) |
56万円 |
|
|
低所得者II |
31万円 |
|
|
低所得者I |
19万円 |
|
- ただし、低所得者Iで介護保険受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
- 医療保険、介護保険ともに自己負担額があり、計算後の支給額が500円以上の場合が対象となります。
- 自己負担額とは、医療機関などに支払った一部負担金(70歳未満の場合、医療保険分については一つの医療機関で同月内に21,000円以上支払った一部負担金が対象となります。)から高額療養費などの払い戻し相当分を差し引いた金額です。
子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
- 国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金を支給します。
- 出産育児一時金の額は、産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合、500,000円です。
- 在胎週数22週未満の出産の場合や、同制度に未加入の医療機関で出産した場合、488,000円です。
- 妊娠4ヶ月(85日)以降であれば、死産・流産でも支給します。
- 社会保険等、他の保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険では支給しません。
直接支払制度
この方法を利用した場合、病院等の窓口負担は、出産育児一時金を超える費用のみです。
入院する際に国民健康保険の保険証等を提示し、病院等との間で、出産育児一時金の申請及び受取に係る代理契約を締結します。
病院等は世帯主に代わって、出産育児一時金を申請し、出産後に病院等が出産育児一時金を直接受け取ります。
直接支払制度を利用しなかった場合又は直接支払制度を利用し、病院等でかかった金額が出産育児一時金の額未満であった場合、世帯主の申請により、出産育児一時金(制度利用の場合は差額)を支給します。
【必要なもの】
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 世帯主名義の普通預金通帳
- 直接支払に関する合意文書
- 出産費用の領収・明細書
- 死産・流産の場合は医師の証明書
- 出産育児一時金申請書(PDF:188KB)
亡くなられたとき(葬祭費)
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行われた方に20,000円を支給します。
【必要なもの】
- 国保の保険証
- 葬儀執行者(喪主)の預金通帳
- 葬儀執行者(喪主)とわかるもの(次のいずれか)
- 会葬礼状(故人、喪主の氏名(フルネーム)が記載されているもの)
- 葬祭の領収書(但書きに「〇〇○○様(故人の氏名(フルネーム))葬儀代」と記載されているもの)
- 死体埋火葬許可証(市民課にて再発行可(手数料必要))
- 死亡を証明するもの(市外で死亡の届出をされたとき)
- 葬祭費支給申請書(PDF:153KB)
いったん医療費を全額自己負担したとき(療養費の支給)
補装具を作成したとき
医師が治療に必要と認めたコルセット等の治療用装具の代金について国民健康保険の負担分を払い戻します。
【必要なもの】
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 世帯主の通帳
- 領収書(領収書に内訳が記載されていない場合は、内訳書も必要です)
- 医証又は診断書等
- 療養費支給申請書(PDF:130KB)
- 装具の写真(靴型装具のみ)※被保険者が実際に装着するものであることが確認できるもの
やむを得ない事情で保険証を持たずに自費で医療機関にかかったとき等
やむを得ず保険証を提示しないで治療を受け、医療費の全額を支払った場合、国民健康保険の負担分を払い戻します。
【必要なもの】
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 世帯主の通帳
- 領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)※開封厳禁
- 療養費支給申請書(PDF:130KB)
海外で医療機関を受診したとき
海外旅行等渡航中に病気やけがのため、やむを得ず海外の病院等で治療を受けた場合、申請により支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。(申請は支払った日の翌日から2年以内です。)
支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められた治療に該当する場合です。
なお、治療目的で出国し、国外の医療機関にかかった場合は制度の対象となりません。
海外療養費は、日本国内に住所のある方が、旅行等で短期間国外に行ったときに治療を受けた場合に給付される制度で、長期間(概ね1年以上)国外に居住する場合には制度の対象外となります。
必要なもの
【医科・歯科共通】
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 世帯主の預金通帳
- 現地の医療機関に支払った領収書(原本)
- 治療を受けた方のパスポート
- 療養費支給申請書(PDF:130KB)
- 調査に関わる同意書(PDF:373KB)
【医科の場合】
- 診療内容明細書(FormA)(PDF:9KB)
- 診療内容明細書(日本語訳文)(PDF:31KB)(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
- 領収明細書(FormB)(PDF:8KB)
- 領収明細書(日本語訳文)(PDF:31KB)(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
【歯科の場合】
- 歯科診療内容明細書(FromC)(PDF:345KB)
- 歯科診療内容明細書(日本語訳文)(PDF:197KB)(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
- 領収明細書(歯科)(PDF:11KB)
- 領収明細書(歯科・日本語訳文)(PDF:30KB)(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
翻訳文に、誤訳や翻訳漏れがある場合、海外療養費の支給を受けるうえで不利益を被ることがありますのでご注意ください。
なお、翻訳手数料については申請者の負担となります。
診療内容明細書と領収明細書は、暦の1か月単位で、医療機関ごと、入院・外来別に作成してもらってください。
移送されたとき(移送費)
国民健康保険の被保険者で、医師が認めた重症の人であって、その病院ではできない治療のために緊急やむを得ず、入院や転院をする際の移送に費用がかかったとき、申請し、国民健康保険の保険者が必要と認めた場合には移送費が支給されます。
※認められる場合でも、もっとも合理的な公共交通機関の運賃等の範囲になります。
また、通院の場合や、単に入院・退院をする場合などは対象になりません。
【必要なもの】
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 移送を必要とする医師の証明書
- 移送にかかった費用の領収書
- 移送経路および手段のわかるもの
- 移送費支給申請書(PDF:84KB)
柔道整復師(整骨院、接骨院)や鍼灸(はり・きゅう)、あんま・マッサージの施術を受けるとき
整骨院や接骨院などの柔道整復師による骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けるとき、医師の同意を得て鍼灸(はり・きゅう)、あんま・マッサージの施術を受けるときは、国民健康保険を使える場合があります。
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき
保険が適用されるもの
仕事中や通勤時以外の、外傷性が明らかな下記の負傷の場合は、保険が適用されます。
- 打撲や捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)
- 骨折・脱臼(緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要)
【主な負傷例】
日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして痛みがでたとき
保険が適用されないもの
次のようなケースでは、保険が適用されません。施術費用は、全額自己負担となります。
- 単なる肩こり、筋肉疲労
- 特に原因のわからない痛み
- 脳疾患後後遺症などの慢性病
- 内科的要因からくるこり・痛み
- 症状の改善の見られない長期の施術
- 予防や慰安目的のマッサージ
- 医療機関(病院)で同じ箇所の治療を受けているとき等
鍼灸(はり・きゅう)、あんま・マッサージにかかるとき
鍼灸(はり・きゅう)、あんま・マッサージの施術を受けるときは、医師の同意がある場合に限り、保険が適用されます。
鍼灸(はり・きゅう)で保険が適用されるもの
- 神経痛
- リウマチ
- 頚(けい)腕(わん)症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頸(けい)椎(つい)ねんざ後遺症
あんま・マッサージで保険が適用されるもの
- 筋麻痺(筋肉が麻痺して自由に動けないような症状)
- 関節拘縮(関節が硬くて動きが悪い症状)
柔道整復師(整骨院、接骨院)や鍼灸(はり・きゅう)、あんま・マッサージの施術を受けるときの注意点は下記、厚生労働省のリンクからご確認ください。
厚生労働省ホームページ「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
交通事故などにあったとき(第三者行為による傷病)
交通事故、けんか、食中毒、他人の飼い犬に咬まれたことなど、第三者行為によるケガや病気でマイナ保険証や保険証を使用して治療をした場合、保険者(鹿屋市)への届出が義務付けられています。
示談をした場合は、下記の必要なものと合わせて示談書の写しをご持参ください。
詳しくは、次の手引きをご覧ください。
第三者行為による傷病届の手引き(PDF:2,269KB)
必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 世帯主の認印
交通事故(人身事故扱い)の場合
- 交通事故証明書
- 届出書類一式(PDF:479KB)
交通事故(物件事故扱い)の場合
- 交通事故証明書
- 届出書類一式(PDF:885KB)
交通事故以外(けんか・犬咬み等)の場合
損害保険会社が届出を代行する場合は、次の様式をご利用ください。
下記のファイルに、事前に情報を入力・印刷することで窓口でかかるお客様の時間が軽減されます。ぜひご活用ください。
記入例は「国民健康保険第三者行為による傷病届の手引き」に記載してあります。
- 第三者行為による傷病届(WORD:62KB)
- 事故発生状況報告書/念書(EXCEL:84KB)
- 誓約書(WORD:19KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書(WORD:76KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書記入にあたって(WORD:27KB)
厚生労働大臣指定の特定疾病
人工透析が必要な慢性腎不全・血友病・HIV感染症で、高額な治療を長期間継続して行う必要がある方は、「特定疾病療養受療証」の申請をすることで自己負担限度額が毎月10,000円(ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります(食事療養および生活療養に要する費用は除く。)。
【必要なもの】
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
(申請書を病院に提出し、医師の証明を受けてください。)
マイナ保険証を利用する場合
市役所の本庁や支所で一度手続きをすれば、特定疾病療養受療証を提示しなくても限度額まで抑えることができます。
ただし、医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示し、情報提供に同意することが必要です。
特定疾病療養受療証の提示
マイナ保険証や保険証と一緒に「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することで、限度額まで抑えることができます。
世帯外の方が手続きをする場合
世帯外の方が申請手続きをする場合、下記の書類等が必要です。
限度額適用認定証、食事療養(兼生活療養)標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証の申請
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 世帯主もしくは対象者の本人確認書類(保険証やマイナンバーカード等)または委任状
委任状は、委任する方(世帯主)がすべての欄を記入する必要があります。
給付関係の申請
振込口座が世帯主の場合
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 世帯主または対象者の本人確認書類(保険証やマイナンバーカード等)
- 世帯主の通帳
振込口座が世帯主以外の場合
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 委任状(PDF:119KB)/委任状(記入例)(PDF:127KB)
委任状は、委任する方(世帯主)がすべての欄を記入する必要があります。
ただし、世帯主が自筆不可能といった理由により記入が難しい場合は、来庁者以外の第三者がすべての欄を記入し、委任する方(世帯主)の本人確認書類をお持ちください。
- 振込を希望する通帳
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.
 文字サイズ
文字サイズ