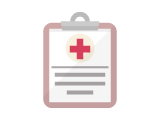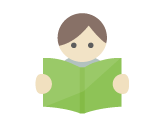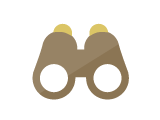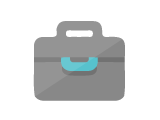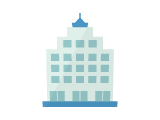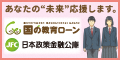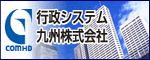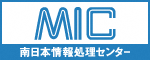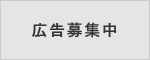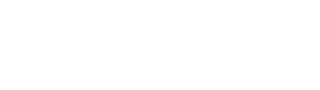更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
高齢者福祉
- 高齢者等介護慰労金の支給
- 紙おむつの支給
- 養護老人ホームへの入所
- 徘徊高齢者位置探索システム端末機貸与事業
- 高齢者生活支援ショートステイ事業
- 緊急通報装置の貸与
- 高齢者等訪問給食サービス事業
- 高齢者在宅生活措置事業
- 障害者控除対象者認定制度
- シルバー人材センター
- 高齢者住宅等安心確保事業(シルバーハウジング)
- 高齢者福祉共通券
- 高齢者おむつ代の医療費控除の取扱いについて
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.
 文字サイズ
文字サイズ