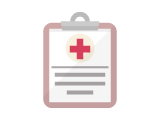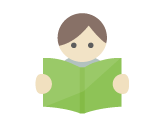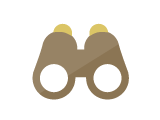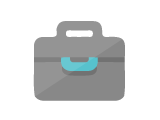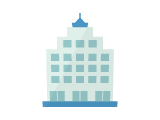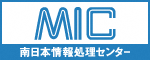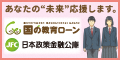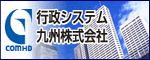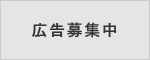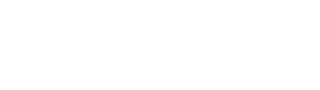近年、「さつまいも」の立枯症状や塊根の腐敗が発生し、収穫が大きく減少するなど被害が拡大しています。
次年度生産に向けてできる対策として、可能な限り下記の対策を徹底してください。
令和8年産に向けて
「今やろう!育苗床の片付けと早期耕うん」(PDF:268KB)
収穫後の病害つるや芋は、ほ場や周辺に残さない
基腐病菌はほ場に残されたさつまいも残渣で越冬し、翌年の伝染源となると考えられています。
そのため、残渣をほ場外に持ち出し適切に処分することが重要です。
生産者が自ら収穫した残さを、肝属地区清掃センターに持ち込む場合は一般廃棄物として有料で持ち込み可能です。
(注意)但し、大量に持ち込みがあった場合は、受入を制限することがあります。
残渣の持出しが困難な場合は、残渣が水分を含んだ状態(概ね収穫後10日以内)で、地温の高い時期に耕耘することで残渣の分解が進みます。
健全な種芋を確保する
- 種いも生産時の感染を防ぐため、「種いも専用ほ場」を設置し、種いもは病害が発生していないほ場からとる。
- 茎頂培養(バイオ)苗を利用し、苗消毒、土壌消毒を実施の上、定植する。
- 蒸熱消毒を9月から11月に実施し、処理後は低温にあたらないように管理する。
「種芋専用ほ場」の条件
- 種芋専用ほ場の条件は前年に水稲を栽培(湛水)した乾田(排水対策を行う。)
- さつまいもを数年栽培していないほ場
- 前作で基腐病等の発生が少なく、排水良好なほ場
育苗床の管理
次年産に健全な苗を確保するため、育苗床の管理を徹底しましょう。
- 当期作の育苗が終わったら、ほ場に埋まった種芋をほ場外へ持ち出し、適切に処分する。
- 残った残渣の分解を促進するため、地温の高い夏場にロータリーで複数回耕うんする。
土壌が乾燥している場合は、かん水を行ってから耕耘する。 - 育苗床は、地温15℃以上、適正な土壌水分(土壌を握りしめ、放したら数個に割れる程度)条件下で、殺菌効果のある剤で土壌消毒又は太陽熱消毒を行う。
- 土壌消毒後は直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で土壌を被覆するなど、使用する土壌消毒剤に応じた適切かつ効果的な使用、作業管理に努める。
土壌消毒剤使用の手引き(PDF:2,151KB)をご確認ください。
病害多発ほ場での輪作、休耕
前作で基腐病が多発し、塊根被害が目立ったほ場では、さつまいも以外の植物を2年程度輪作または休耕することが望ましいと考えられています。
| 関連リンク |
 文字サイズ
文字サイズ