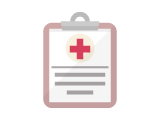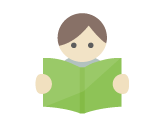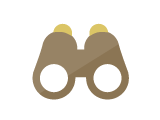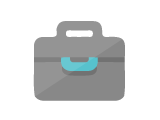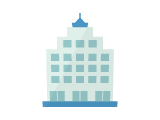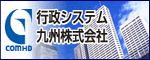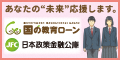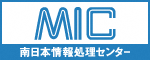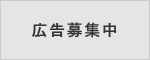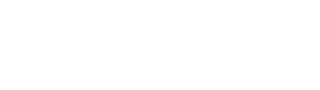更新日:2026年2月18日
ここから本文です。
新型コロナウイルス予防接種
- 令和7年度の新型コロナウイルス予防接種の公費助成は終了しました。
令和7年度の新型コロナウイルス予防接種は、新型コロナウイルス感染症が予防接種法のB類疾病と位置付けられ、個人の重症化予防を目的とする「定期接種」となり、接種に努力義務はなく、希望する方のみに行います。
接種については、メリット(重症化予防)とデメリット(副反応)を理解した上で、慎重にご判断ください。
今年度の新型コロナウイルス予防接種につきまして、次のとおりお知らせします。
【厚生労働省】新型コロナワクチンリーフレット(令和7年10月版)(PDF:1,902KB)
|
接種対象者 |
(1)接種日において、65歳以上の人 (2)接種日において、60~64歳の人 注)心臓・腎臓疾患などがある人は、病状によりワクチン接種に注意が必要です。 |
| 接種時期 |
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで 注)上記期間外の接種については、公費負担の対象になりませんのでご注意ください。 |
| 接種回数 | 1人1回のみ |
| 自己負担額 |
注)ただし、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付受給者については、全額公費負担(無料)となりますので、協力医療機関へ受給証明書を提出してください。 |
| 協力医療機関 |
新型コロナウイルス予防接種協力医療機関一覧(PDF:461KB) 注)接種費用等(ワクチンの種類や予約受付開始日など)を確認し、事前予約をしてください。 |
| 使用ワクチン |
<添付文書>
<ワクチン接種を受ける人へのガイド> |
| 注意事項等 |
|
|
予診票等 (参考) |
|
| 任意接種 |
|
予防接種を受ける前に
- 接種回数は本期間中(10月1日から翌年1月31日まで)1人1回のみのため、誤って2回以上の接種とならないよう、十分に注意してください。
- 新型コロナワクチンの予防接種について、必要性や副反応等を上記説明書等をよく読んで理解した上で、自らの意思で接種するかしないかを判断してください。
- ワクチン接種は体調のよいときに受けるのが基本ですので、特に基礎疾患のある人は、病状が悪化していたり、全身が衰弱している場合は避けた方がよいと考えられます。気にかかることや分からないことがあれば、あらかじめかかりつけの医師に相談し、十分に納得できない場合は、接種を控えてください。
新型コロナウイルス予防接種の効果
- オミクロン株流行下での感染を予防する効果(感染予防効果)や感染しても発症を予防する効果(発症予防効果)の持続期間が2~3か月程度と限定的である一方、発症しても重症化を阻止する効果(重症化予防効果)は、1年以上一定程度持続するとされています。
新型コロナウイルス予防接種後の副反応について
- 新型コロナワクチンの主な副反応として、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。
- 稀な頻度でショックやアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生したことが報告されています。接種後に気になる症状を認めた場合は接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
- mRNAワクチンでは、頻度としてはごく稀ですが、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。ワクチン接種後数日以内に胸の痛みや息切れなどの症状が現れた場合は、速やかに医療機関に連絡してください。
予診票の記入について
- 予診票は、接種をする医師にとって、予防接種の可否を決める大切な情報です。接種を受ける方が責任をもって記入し、正しい情報を医師に伝えてください。
- 必ず、ボールペンで記入してください。
- 予診票は、本人が書くことが原則です。代筆をお願いする場合は、接種を受ける人の状況がよくわかる人で、(1)家族又は親戚(2)身の回りの世話をしている人(介護者等)が代筆できます。
予防接種を受けることのできない人
- 接種当日、明らかに発熱している人
- 重い急性疾患にかかっている人
- ワクチンの成分に対しアナフィラキシーなど重度の過敏症(※)の既往歴のある人
- その他、医師が接種不適当な状態と判断した場合
※アナフィラキシーや、全身の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる全身の症状。
予防接種を受ける前に担当医師とよく相談をしなくてはならない人
- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障がいのある人
- 過去に免疫不全の診断がされている人及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障がい等の基礎疾患のある人
- 過去にけいれんをおこしたことのある人
- 新型コロナワクチンの成分に対してアレルギーがある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性発疹等のアレルギーを疑う症状がでたことがある人
- その他、体調のことで心配のある人
予防接種を受けた後の一般的注意事項
- 接種を受けた後30分程度は、急な副反応がおこることがありますので、医療機関内で様子をみられるか、医師(医療機関)とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
- お風呂は入ってもかまいませんが、注射した部位を強くこすらないで、短時間の入浴にしてください。
- 接種当日は、いつも通りの生活をしてかまいませんが、安静に過ごすように心がけ、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- 接種後に、接種したところの異常反応や体調に変化があった場合は、速やかに医師(医療機関)の診察を受けてください。
予防接種健康被害救済制度
予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。
極めてまれですが、不可避的に生ずるものであるため、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づく予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
(疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、救済は受けられません。)
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.
 文字サイズ
文字サイズ