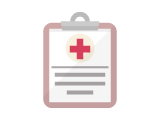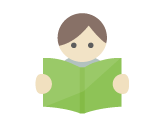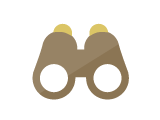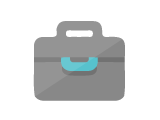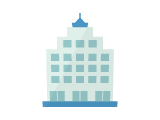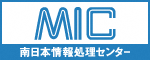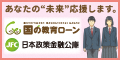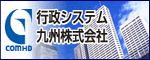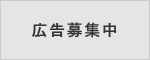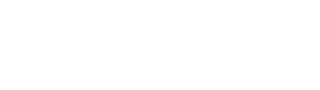更新日:2024年8月6日
ここから本文です。
活動報告(令和6年7月)
7月1日(月曜日):辞令交付式(地域おこし協力隊)

本市出身の永吉裕之さん(44歳)を鹿屋市地域おこし協力隊(有害鳥獣ハンター)に任命しました。
本市は、農業や畜産業を基幹産業とする産地でありますが、近年、鳥獣による農作物被害が増加していますが、被害軽減に取り組む猟友会員の高齢化等、担い手の減少が深刻化しています。
このようなことから、今回任命した地域おこし協力隊においては、有害鳥獣捕獲に関するノウハウのほか、ジビエの加工・販売や枝物の生産・販売に関するノウハウを習得し、地域住民と一体となり有害鳥獣被害対策に取組むこととしており、今後の被害防止対策が推進されることを期待いたします。
7月1日(月曜日):第74回「社会を明るくする運動」メッセージ伝達式及び出発式

第74回「社会を明るくする運動」メッセージ伝達式及び出発式に出席いたしました。
この運動は、全ての国民が、犯罪や非行防止、罪を犯した人たちの更正について理解を深め、それぞれの立場で、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
本市においては、再犯を防止することにより市民が安全で安心して暮らせる社会の実現を図るため、昨年「鹿屋市再犯防止推進計画」を策定したところです。
今後においても、誰もが安心して幸せに暮らせる明るい地域社会づくりに、保護司会の皆様や、更生保護女性会の皆様をはじめ、関係団体等と一体となり取り組んでまいります。
7月10日(水曜日):(面会)有限会社サンフィールズ

令和3年から輝北町でメロンの栽培に取り組まれている、有限会社サンフィールズ久木田代表取締役に、令和6年産の生産概況等の報告にお越しいただきました。
耐暑性に優れ、幅広い作型に対応する赤肉ネットメロン(品種:キャサリンレッド)や白肉メロン(品種:AM55)をご紹介いただきました。
コンビニエンスストアや福岡空港内での販売等を予定しており、今後、本市産のメロンが多くの消費者を喜ばせることを期待いたします。
7月11日(木曜日):令和6年度全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会総会
全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会総会に出席いたしました。
この協議会は、国立のハンセン病療養所の所在する12市町で構成され、共通する課題について協議し、その解決を図るとともに、所在市町の連携、協力及び相互支援を目的に設立されました。
総会においては、元患者や家族への差別解消や、入所者の生活環境整備などを国に求める決議を採択しました。
引き続き、関係自治体や機関と連携するとともに、学校教育や啓発事業を通じた偏見や差別の解消を推進するなど、とともに、取り組んでまいります。
7月14日(日曜日):かのやマリンフェスタ2024

かのやマリンフェスタは、平成9年の高須艇庫の完成を機にはじまり、今では、本市に夏の訪れを告げる一大イベントとして定着しています。
子どもから大人まで多くの市内外の皆様が、例年ご好評いただいている、バナナボートやビーチサンダル飛ばしなど、マリンスポーツ・イベントをお楽しみいただきました。
本イベントの開催にあたり、鹿屋体育大学の多くの学生の皆様や、高須・浜田両町内会をはじめ、協賛・協力いただきました皆様に、心より感謝申し上げます。
7月16日(火曜日):スポーツ推進審議会委嘱状交付式
スポーツ基本法第31条などの規定に基づき設置する、スポーツ推進審議会の委員の皆様に委嘱状を交付いたしました。
この審議会は、鹿屋市のスポーツ施設や設備の整備、指導者の養成や資質の向上、事業の実施及び奨励、団体の育成、事故の防止、技術水準の向上などについて審議し、建議するために設置しています。
スポーツは、体力向上や健康増進はもとより、青少年の健全育成、生きがいや仲間づくりといった地域コミュニティを創出することや、スポーツを通じた交流人口の増加による地域経済の活性化など、多岐にわたって効果をもらたします。
今回、委員をお引受けいただいた皆様には、忌憚のないご意見をいただき、本市のスポーツ振興にお力添えいただくことを期待しております。
7月17日(水曜日):第19回串良川クリーン作戦

今回で19回目を迎える、串良川クリーン作戦に参加いたしました。
近年は、コロナ禍の影響により、開催を見送っておられましたが、住民の河川環境問題に関心を持っていただきたいとの思いから、東串良町商工会様及び、かのや市商工会様に、5年ぶりに美化清掃作業を計画をいただき、心より感謝申し上げます。
本市ににおきましても、環境基本計画に基づき、市民の皆様や各事業所、関係機関と連携を図り、豊かな自然環境の保護、そして快適で潤いのある住環境の整備に努めてまいります。
7月17日(水曜日):鹿屋市国民健康保険運営協議会委嘱状交付式
鹿屋市国民健康保険運営協議会の委員の改選に伴い、委員の皆様に委嘱状を交付いたしました。
国民健康保険制度は、誰もが必要な時に必要な医療を少ない負担で受けられる国民皆保険制度の基盤をなすもので、地域医療の確保と市民の健康維持増進に大変重要な役割を担っております。
本市では、本年3月に第3期となる、鹿屋市国民健康保険保健事業実施計画を改定し、特に、市民の健康寿命延伸のため、特定検診の受診率向上に引き続き取り組むこととしております。今後におきましても、協議会をはじめ、地域の医療等関係者と連携を図り、制度の安定的な運営に取り組んでまいります。
7月17日(水曜日):(面会)鹿屋女子高等学校スーパービジネスクラブ

第71回鹿児島県高等学校ビジネス計算競技大会及び、第71回鹿児島県高等学校ワープロ競技大会において、団体総合(電卓の部)競技優勝のほか各部門において優秀な成績を収められた、鹿屋市立鹿屋女子高等学校の部活動であるスーパービジネスクラブの皆さんにお越しいただきました。
部活動では、ビジネスのスペシャリストの育成を目指し、商業に関する知識や技術の習得に力を入れており、競技会で活躍と資格取得を両立して日々練習に励んでいるとのことでした。
今後、沖縄県での九州大会、神奈川県での全国大会へ出場を予定しており、今後ますますのご活躍を期待いたします。
7月21日(日曜日):肝属川クリーン作戦

肝属川クリーン作戦は、潤いのあるきれいな肝属川を守ることを目的として、昭和57年に「小さな親切運動」の一環として始まり、今回で41回目の開催となりました。早朝より、地域の住民や事業所等の64団体957人の方々にお集まりいただき、活動いただいたことに感謝申し上げます。
前回から「ウォーキングごみ拾い」というテーマを掲げ、広く多くの方々に気軽にごみ拾いに参加していただき、肝属川の周辺のみならず、街中や地域における環境美化についても関心を持っていただきたいという願いが込められています。
引き続き、未来の子どもたちに豊かな自然や資源を引き継ぐためにも、環境保全活動を推進してまいります。
7月22日(月曜日):鹿屋警察署管内国際化対策連絡協議会役員会及び総会
鹿屋警察署管内国際化対策連絡協議会役員会及び総会が開催されました。
本市はもとより、県内の外国人在住者の人口は増加傾向にあります。また、県内の外国人労働者は、届出が義務化された平成19年以降、初めて1万人を超え、過去最高を更新しているとこでございます。
今後におきましても、協議会での活動や、関係機関との連携を通じて、市民と外国人がともに安心して安全に暮らすことのできる環境づくりに取り組んでまいります。
7月25日(木曜日):鹿児島県市議会議長会定期総会
本市において、鹿児島県市議会議長会定期総会を開催いただきました。
それぞれの地域においては、共通して、少子高齢化や人口減少、物価高騰への対応を始めとして、社会経済情勢が大きく変化する中で、多岐にわたる諸課題に直面している状況にあります。
このような中、地域の抱える様々な課題を国・県に対し要望するために審議される大事な会であり、議長会を通じ、地域の願いを国県等関係機関に対し万全で望まれることをお願いさせていただきました。
7月26日(金曜日):令和6年度鹿屋市と国立大学法人鹿屋体育大学との連携協議会
国立大学法人鹿屋体育大学との連携協議会を開催いたしました。
この会が発足し、今年で14年目となり、これまで市民が参画できるスポーツイベントの開催や、スポーツを軸とした地域づくりに取り組んでまいりました。
スポーツの力で地域を元気づけ、活力ある社会を実現するため、産官学連携をより一層強化し、様々なスポーツ施策の推進に取り組んでまいります。
7月28日(日曜日):鹿児島県消防協会肝属支部操法大会
鹿児島県消防協会肝属支部操法大会を開催いたしました。
消防団の皆様におかれましては、地域に根差した消防として、昼夜を問わず、住民の生命・財産を災害等から守るため日々貢献していただいていることに深く感謝申し上げます。
この大会は、消防団員のポンプ操法技術の向上を図り、火災時の消火活動を万全なものにし、併せて消防団の士気の高揚と地域住民の信頼を高めることを目的として開催しており、消防操法の基本である、「安全」「確実」「迅速」をモットーに各チーム一生懸命に競技していただきました。
7月29日(月曜日):第1回鹿屋市総合教育会議

令和6年度第1回鹿屋市総合教育会議を開催いたしました。
近年のライフスタイルの多様化など、子育て環境をはじめ、学校や地域社会における子どもの育ちを巡る環境は、急激に変化しています。
国においては、こどもまんなか社会の実現に向けた取り組みを推進しており、本市におきましても、本年4月から、子育て世帯へ包括的な相談支援を行う機関として「鹿屋市こども家庭センター」を開設し、子育てに関する相談や虐待、貧困などの様々な課題に対応する窓口を設けるなどの取り組みを行っています。
このような中、会議においては、第3期教育大網の基本理念や基本目標等に関する意見交換のほか、本市の教育行政における現状と課題及び重点事項の共有と意見交換などを行いました。
引き続き、市長部局と教育委員会が連携を図り、教育政策に取り組んでまいります。
7月30日(火曜日)、7月31日(水曜日):大隅総合開発期成会等中央要望

大隅地域の最重点要望事項の実現を図るため、国や関係機関等に対し、所要の予算措置等が行われるよう、大隅半島4市5町で構成する大隅総合開発期成会をはじめとした関係団体合同により、首長・議長、経済団体の代表等が要望活動を行いました。
大隅地域が一体となり、地域の課題解決に取り組むとともに、それぞれの地域資源や特性を活かし、地域の活性化や産業の振興、住民の所得向上や雇用の促進等につなげ、活力ある大隅地域の発展を築くことができるよう、引き続き、近隣市町をはじめ関係機関・団体と連携して取り組んでまいります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
- 活動報告(令和7年12月)
- 活動報告(令和7年11月)
- 活動報告(令和7年10月)
- 活動報告(令和7年9月)
- 活動報告(令和7年8月)
- 活動報告(令和7年7月)
- 活動報告(令和7年6月)
- 活動報告(令和7年5月)
- 活動報告(令和7年4月)
- 活動報告(令和7年3月)
- 活動報告(令和7年2月)
- 活動報告(令和7年1月)
- 活動報告(令和6年12月)
- 活動報告(令和6年11月)
- 活動報告(令和6年10月)
- 活動報告(令和6年9月)
- 活動報告(令和6年8月)
- 活動報告(令和6年7月)
- 活動報告(令和6年6月)
- 活動報告(令和6年5月)
- 活動報告(令和6年4月)
- 活動報告(令和6年3月)
- 活動報告(令和6年2月)
- 活動報告(令和6年1月)
- 活動報告(令和5年12月)
- 活動報告(令和5年11月)
- 活動報告(令和5年10月)
- 活動報告(令和5年9月)
- 活動報告(令和5年8月)
- 活動報告(令和5年7月)
- 活動報告(令和5年6月)
- 活動報告(令和5年5月)
- 活動報告(令和5年4月)
- 令和4年度
- 活動報告(令和5年3月)
- 活動報告(令和5年2月)
- 活動報告(令和5年1月)
- 活動報告(令和4年12月)
- 活動報告(令和4年11月)
- 活動報告(令和4年10月)
- 活動報告(令和4年9月)
- 活動報告(令和4年8月)
- 活動報告(令和4年7月)
- 活動報告(令和4年6月)
- 活動報告(令和4年5月)
- 令和3年度
- 活動報告(令和4年4月)
- 活動報告(令和4年3月)
- 活動報告(令和4年2月)
- 活動報告(令和4年1月)
- 活動報告(令和3年12月)
- 活動報告(令和3年11月)
- 活動報告(令和3年10月)
- 活動報告(令和3年9月)
- 活動報告(令和3年8月)
- 活動報告(令和3年7月)
- 活動報告(令和3年6月)
- 活動報告(令和3年5月)
- 令和2年度
- 平成25年度
- 活動報告(令和3年4月)
- 活動報告(令和3年3月)
- 活動報告(令和3年2月)
- 活動報告(令和3年1月)
- 活動報告(令和2年12月)
- 活動報告(令和2年11月)
- 活動報告(令和2年10月)
- 活動報告(令和2年9月)
- 活動報告(令和2年8月)
- 活動報告(令和2年7月)
- 活動報告(令和2年6月)
- 活動報告(令和2年5月)
- 平成26年度
- 平成27年度
- 平成28年度
- 平成29年
- 平成30年度
- 令和元年度
- 活動報告(令和2年4月)
- 活動報告(令和2年3月)
- 活動報告(令和2年2月)
- 活動報告(平成29年10月)
- 活動報告(平成29年11月)
- 活動報告(平成28年6月)
- 活動報告(平成28年7月)
- 活動報告(平成28年8月)
- 活動報告(平成28年5月)
- 活動報告(平成27年12月)
- 活動報告(平成28年1月)
- 活動報告(平成28年2月)
- 活動報告(平成28年4月)
- 活動報告(平成28年3月)
- 活動報告(平成28年9月)
- 活動報告(平成28年10月)
- 活動報告(平成29年6月)
- 活動報告(平成29年7月)
- 活動報告(平成29年8月)
- 活動報告(平成29年9月)
- 活動報告(平成29年5月)
- 活動報告(平成29年4月)
- 活動報告(平成28年11月)
- 活動報告(平成28年12月)
- 活動報告(平成29年1月)
- 活動報告(平成29年3月)
- 活動報告(平成29年2月)
- 活動報告(平成27年11月)
- 活動報告(平成27年10月)
- 活動報告(平成26年8月)
- 活動報告(平成26年9月)
- 活動報告(平成26年10月)
- 活動報告(平成26年7月)
- 活動報告(平成26年6月)
- 活動報告(平成26年2月)
- 活動報告(平成26年3月)
- 活動報告(平成26年4月)
- 活動報告(平成26年5月)
- 活動報告(平成26年11月)
- 活動報告(平成26年12月)
- 活動報告(平成27年7月)
- 活動報告(平成27年8月)
- 活動報告(平成27年9月)
- 活動報告(平成27年6月)
- 活動報告(平成27年5月)
- 活動報告(平成27年1月)
- 活動報告(平成27年2月)
- 活動報告(平成27年3月)
- 活動報告(平成27年4月)
- 活動報告(平成30年2月)
- 活動報告(平成30年1月)
- 活動報告(平成29年12月)
- 活動報告(平成31年4月)
- 活動報告(平成31年3月)
- 活動報告(平成31年2月)
- 活動報告(令和元年5月)
- 活動報告(令和元年6月)
- 活動報告(令和元年9月)
- 活動報告(令和元年7月)
- 活動報告(令和元年8月)
- 活動報告(平成31年1月)
- 活動報告(平成30年12月)
- 活動報告(平成30年5月)
- 活動報告(平成30年4月)
- 活動報告(平成30年3月)
- 活動報告(平成30年6月)
- 活動報告(平成30年11月)
- 活動報告(平成30年10月)
- 活動報告(平成30年9月)
- 活動報告(平成30年7月)
- 活動報告(平成30年8月)
- 活動報告(令和元年12月)
- 活動報告(令和元年11月)
- 活動報告(令和元年10月)
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.
 文字サイズ
文字サイズ